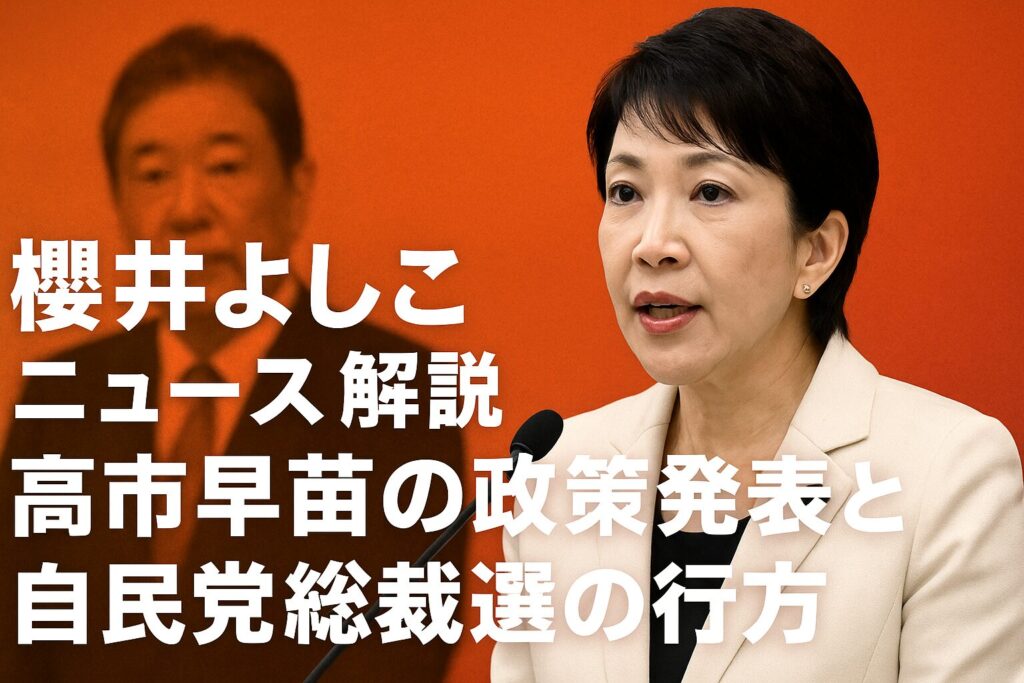
自民党総裁選を前に、高市早苗氏が打ち出した包括的な政策発表が大きな注目を集めています。経済から安全保障、さらには女性の健康や食料・エネルギー問題まで、多岐にわたる政策を明確に提示し、記者からの厳しい質問にも冷静に応じた姿勢は、多くの党員や有権者に強い印象を残しました。
これに対し、石破茂氏や小泉進次郎氏らの動きも加速し、党内の駆け引きは一層激しくなっています。櫻井よしこ氏は、自らの取材を交えて「地方党員票がカギを握る」と分析。
果たして、次期総裁の座をめぐる戦いはどのような展開を迎えるのか。その背景と行方を探ります。
高市氏の政策発表――全体像
高市氏は約1時間半の記者会見で、経済(生活支援・積極財政)/経済安全保障・防衛/食料安全保障/エネルギー政策/女性の健康や社会参加など、幅広い分野にわたる政策の方向性と具体案を提示しました。記者からの鋭い問いにも落ち着いて答え、連立政党である公明党の懸念にも配慮を示す発言をしています。(朝日新聞)
1) 経済政策:給付付き税額控除など「手取りを増やす」方針
何を言ったか
- 「給付付き税額控除」の制度設計に着手すると明言。これは低〜中所得層に対し、税制上の控除+現金給付で可処分所得を直接増やす仕組みです。(朝日新聞)
- ガソリン減税や自治体への重点支援交付金の拡充、年収の課税最低ライン(「年収の壁」)の引き上げなど、消費者の実感に届く措置を検討しています。(朝日新聞)
なぜこれを打ち出したか(狙い)
- 物価高・生活コスト上昇が有権者の最大の関心事になっているため、短期的に手取りを増やす政策で支持を固める狙い。党内の地方党員や生活実感を重視する層を取り込みやすい。選挙戦略としては「即効性のある経済対策」で他候補との差別化を図る意図が読み取れます。(Yahoo!ファイナンス)
実現性と課題
- 給付付き税額控除は概念的には所得再配分に有効だが、財源確保(財政負担)と制度設計の複雑さが課題。消費税を減税するか、他の歳出を削るか、あるいは国債発行を増やすかの議論が必要になります。与党内・連立相手との調整が不可欠です。(朝日新聞)
2) 安全保障・経済安全保障:産業育成と中国対応のバランス
具体案
- AI、半導体など成長分野への官民連携による積極投資を掲げ、経済安全保障を強化する姿勢を強調。外国からの重要分野への投資管理やサプライチェーンの強化も含まれる方向です。(朝日新聞)
- 中国との関係については「長い歴史を持つ隣国として良好な関係を保つ必要があるが、日本の立場もきちんと主張する」「国家情報法や国防関連の法整備を念頭に、対話を重ねる」といったバランスの取れた文言で説明しています。(朝日新聞)
なぜ重要か(効果)
- 技術・サプライチェーン面での自立強化は、地政学的リスクが高まる現代において国の安全に直結します。民間資金を呼び込みつつ規制で重要技術を守る、という二重戦略は先進国でよく採られる手法です。(X (formerly Twitter))
課題と政治的含意
- 対中政策は「強硬一辺倒」に傾くと経済面の摩擦を招く一方、甘ければ安全保障上の懸念を生むため微妙な均衡が必要。高市氏の表現は慎重で、対話と主張を両立する姿勢を取っていますが、実務では米国との連携や国内の法整備(対中投資規制や反スパイ法など)の整合が試されます。(朝日新聞)
3) 食料・エネルギー:安全保障の延長としての供給確保
具体案
- 食料安全保障の強化(農業の集約化・大規模化への投資、国内生産力の強化)を掲げています。エネルギーでは、供給の安定化や次世代原子力(研究開発)の推進に言及しています。(朝日新聞)
なぜこれが出てくるのか
- 食料・エネルギーは地政学的ショックや国際市場の変動で直ちに国民生活に影響が出る分野。安全保障観点からも**「国の基盤を守る」政策**として有権者にアピールしやすい分野です。(朝日新聞)
実務課題
- 農業の大規模化は効率化につながるが、地域社会・小農家の反発や環境負荷の問題もあるため、**制度設計(補助・再編・所得補償など)**が重要になります。エネルギー面は技術投資の長期性と安全性の確保が鍵です。(朝日新聞)
4) 女性の健康・社会参加:政策の広がりと支持層拡大狙い
具体案
- 女性の健康問題を政策の一項目として明記し、女性が働きやすく・健康に暮らせる環境整備を訴えました(医療・働き方・支援策の充実)。(朝日新聞)
なぜ出すのか
- これは単に社会政策というだけでなく、支持基盤の広がりを狙う戦略でもあります。保守層だけでなく、女性層や生活実感を重視する有権者を取り込む意図が伺えます。(Yahoo!ファイナンス)
公明党の発言と連立の観点――「穏健保守でなければ連立しない」
公明党の動き
- 公明党代表が「我々の理念に合う人物でなければ連立政権は組めない」と述べ、連立の継続条件として「穏健/保守中道」を強調しています。これが高市氏の政策とどう合うかが注目点です。(TBS NEWS DIG)
政治的含意
- 自公連立が崩れる場合、政権運営の安定性に重大な影響が出ます。高市氏は連立の重要性を認めつつ(連立を基軸にすると発言)、政策面では自らの路線を打ち出すという両立を図っています。連立相手の要求にどこまで歩み寄るかが焦点です。(朝日新聞)
ポイント
- 選挙戦略としての特徴:高市氏の発表は「生活実感に届く経済対策+経済安全保障の強化」という二本立てで、地方党員や保守層にアピールする構図。短期効果と中長期の国家戦略を同時に訴える形です。(朝日新聞)
- 実現の壁:給付付き税額控除などは有効性がある一方で財源と制度設計、連立調整という現実的なハードルがあります。政策の詳細な「数字」(財源試算)が鍵になります。(朝日新聞)
- 外交・安保のバランス:対中関係や安全保障では「強さ」と「対話」の両立を目指しており、米国との連携や国内法整備との整合が重要になります。(X (formerly Twitter))
- 政治的影響:公明党の条件や石破氏らの動き(党内の駆け引き)を踏まえ、政策実現力は「党内票と連立の支持」をどう確保するかに依存します。(TBS NEWS DIG)
石破氏の行動は?
報道や関係者の証言によれば、石破茂氏は地方の自民党員に直接電話をかけ、
「高市早苗氏には投票しないでほしい。むしろ林芳正氏や小泉進次郎氏を支持してほしい」
と働きかけているとされています。
👉 つまり石破氏は「自分が総裁選に出ない立場」でも、裏で影響力を行使しようとしているということです。
2. なぜこんな行動を取るのか?
石破氏がこのような行動を取る背景には、いくつかの理由が考えられます。
- 過去の確執
高市氏とは政策スタンスが大きく異なり、特に安全保障・憲法観で対立してきました。石破氏の支持者の中には「タカ派色が強い高市氏を総裁にしたくない」という意識があります。 - 自らの影響力を示したい
石破氏は一時期「地方に強い政治家」と呼ばれ、党員票で安倍晋三氏に迫った実績もあります。今回の総裁選でも「自分の推薦で票が動いた」という実績を残すことで、存在感を保ちたい狙いがあるとみられます。 - 将来のポジション取り
自らは出馬しなくても、勝った候補とパイプを持っておけば、将来的に党内で役職や影響力を得ることにつながります。
3. 実際の影響力はどうなのか?
専門家の見方は厳しく、
「石破氏の影響力は以前ほど強くない」
とされています。
- ピークは2012〜2020年
当時は「地方党員票で圧倒的に強い」と言われ、安倍政権に対抗するポジションを築いていました。 - 現在は低下傾向
長期的に派閥を持たず、安倍派など保守系の基盤とも距離を置いたため、党内で頼れる組織力が乏しい状態。
また、支持者が期待した「自民党改革」も成果が乏しく、地方でも「石破待望論」は薄れています。 - 票を大きく動かす力は弱い
電話一本で投票行動を変えるほどの求心力はなく、むしろ「まだ影響力を残そうとしている」と見られがち。
4. 背景にある党内力学
- 石破氏は自民党内で「反主流派」として存在感を保ってきましたが、主流派(安倍派や麻生派など)と距離を置いた結果、孤立気味になっています。
- 今回は「誰を推すか」で動き回っていますが、党内では「もう以前ほど地方党員票を動かせないのでは」と冷ややかに見られるケースが多いです。
- このため、石破氏の働きかけが「逆効果」になる可能性すら指摘されています。つまり「石破氏が推すなら逆に支持をやめよう」と考える人がいるわけです。
前回総裁選での党員票の位置づけ
- 前回の総裁選では、高市早苗氏と石破茂氏が「地方党員票」で接戦を演じ、高市氏が僅差で上回りました。
- この結果は、当時から「高市氏が保守層に強い浸透力を持っている」ことを示していました。
- 石破氏はそれまで「地方党員票に強い政治家」と呼ばれてきましたが、前回選挙でそのブランドが揺らいだ格好です。
今回の特徴:保守票の再結集
- 今回は状況が変化しています。
- 自民党を離党して参政党や保守新党に流れた元党員層
- 無所属化した元党員(=党費を払わなくなったが政治的には保守寄り)
これらの人々が「総裁選では再び高市氏を後押しする」可能性が高いと指摘されています。
- 特に参政党や保守系新党を支持していた人々は、政策面で「憲法改正」「防衛力強化」「エネルギー自立」など高市氏のスタンスと親和性が高い。
- この層が「今回は自民党の中からでも保守的な選択をすべきだ」と考え、高市支持に回るとみられます。
地方党員票での優位性
- 自民党総裁選は「党員票」と「国会議員票」の二本立て。
- 地方党員票で圧倒的に勝利する候補は、最終的に国会議員票でも「勝ち馬に乗る」形で支持を広げやすい、というのが過去の選挙パターンです。
- 例:小泉純一郎氏の総裁選(2001年)は、地方党員票の圧勝で国会議員の支持も雪崩のように移り、大勝に結びつきました。
- 今回も同様に、地方で高市氏が「盤石な勝利」を収めれば、国会議員が最終的に高市氏に流れる可能性は極めて高いと見られています。
党員票が持つ“風”の効果
- 党員票は数的には国会議員票と釣り合いませんが、「選挙に強い候補」を示すシグナルになります。
- 地方票で勝った候補=国民的人気がある、と党内で評価されやすいため、議員たちは「次の衆院選を戦う上で有利かどうか」を判断基準にします。
- その意味で、高市氏が地方票で圧勝できれば、それ自体が国会議員を引き寄せる武器になるのです。
ポイント
高市氏は前回の総裁選で石破氏を僅差で上回り「地方票に強い候補」であることを示しました。
今回はさらに、参政党や保守新党に流れた元党員、無所属の保守層が加わり、地方党員票での優位性を一層強めると予想されます。
もし地方票で圧勝できれば、その“風”に乗って国会議員票も高市氏に流れ、総裁選全体で主導権を握る可能性が高い――これが専門家の分析です。
小泉進次郎氏の戦略とは?
次期総裁選を見据え、小泉進次郎氏の動きが注目を集めています。彼がとっている戦略の大きなポイントは「リベラル色を封印し、保守層にアピールする姿勢」を強めていることです。
1. リベラル色を抑え、保守寄りへシフト
小泉氏といえば、これまで「環境政策」や「脱炭素」「多様性」といった比較的リベラルなイメージで注目されてきました。特に若者や都市部の支持を集めやすい立場でしたが、一方で保守的な自民党の岩盤支持層には距離がありました。
そこで今回は、そのリベラル色を前面に出すのではなく、むしろ「保守的価値観」を尊重する姿勢を示しているのです。これは総裁選で票を得るために、党内の保守派議員や支持団体を取り込む狙いがあると考えられます。
2. 選対本部長に加藤勝信財務大臣を起用
さらに注目なのが「選挙対策本部長」に現職の財務大臣・加藤勝信氏を起用した点です。
通常、現職の閣僚が選対の中心に入ることは珍しく、賛否が分かれるところです。
- メリット:政権中枢にいる閣僚を取り込むことで「安定感」「政権経験の厚さ」をアピールできる。
- デメリット:公私の線引きが曖昧になり、政治と行政の混同と批判される可能性がある。
つまり小泉氏は、「自分は若手でありながらもベテラン閣僚と連携できる人物だ」ということを示し、幅広い層にアピールしているわけです。
ポイント
小泉進次郎氏の戦略は、これまでの“改革派・リベラル”というイメージから一歩引き、党内保守層に寄り添う姿勢を見せることで、総裁選に必要な票を固めにいくものです。そして、財務大臣を選対本部長に迎え入れるという布陣は、彼の本気度を示すと同時に、政治的リスクも抱えています。
今後、これが支持拡大につながるのか、それとも批判を呼ぶのかが注目されます。
最後に
今回の総裁選で最大のカギを握るのは、やはり「地方党員票」です。国会議員票は派閥の力学で大きく動きますが、地方党員票は草の根の支持を色濃く反映するため、候補者の“本当の支持基盤”を測る試金石となります。
櫻井よしこ氏が指摘するように、高市早苗氏がこの地方党員票で圧倒的な勝利を収められるかどうかが、最終的な決戦投票を制する決め手になるのです。言い換えれば、地方票で突き抜けることができなければ、党内での派閥間の駆け引きに埋没し、勝ち筋を失う危険すらあるということ。
総裁選は単なる権力争いではなく、自民党の今後の路線、そして日本の進路を左右する大きな分岐点です。地方の声をどこまで取り込めるか――この一点が、次の日本のリーダーを決定づける最大の焦点となるでしょう。
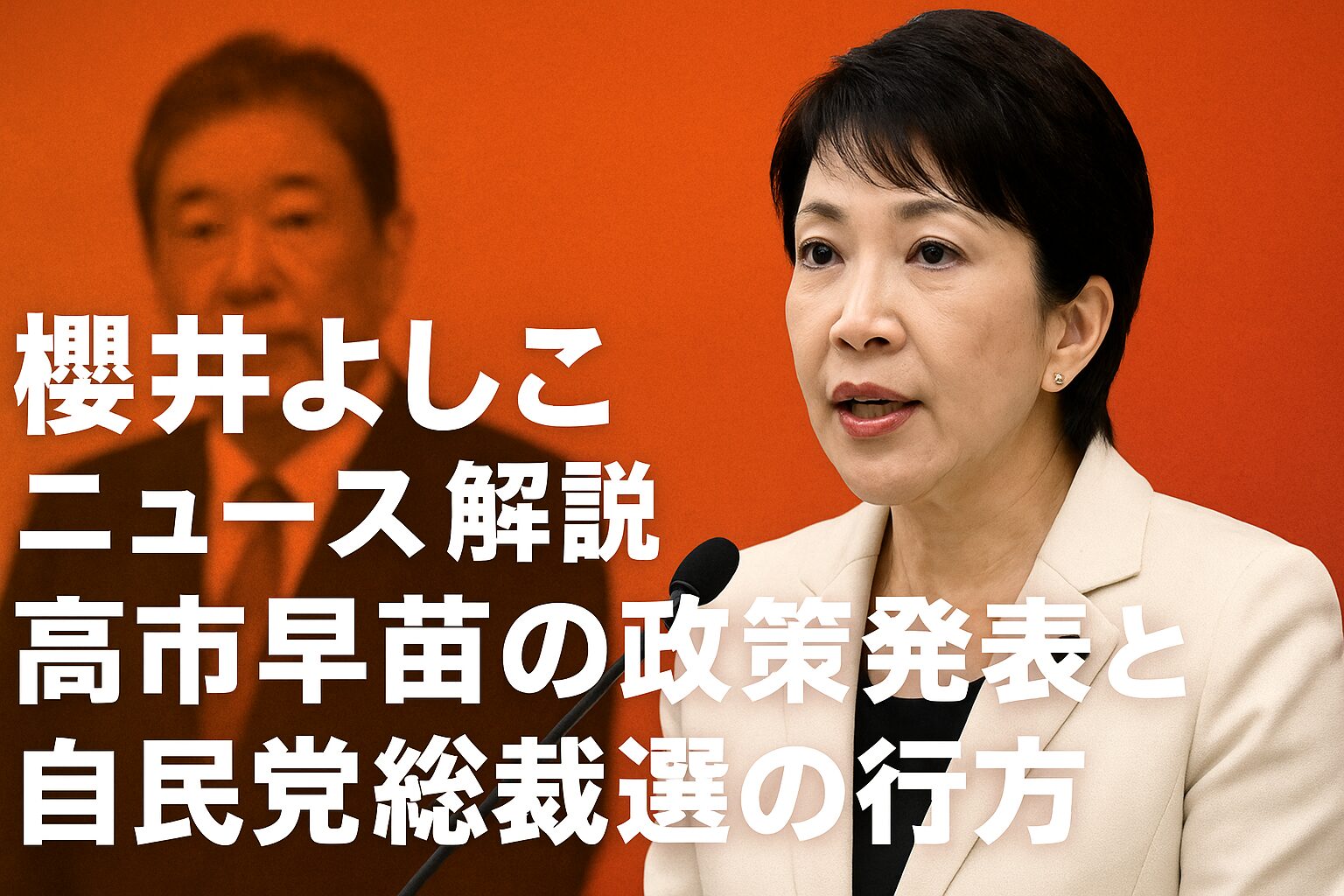
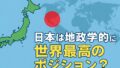

コメント