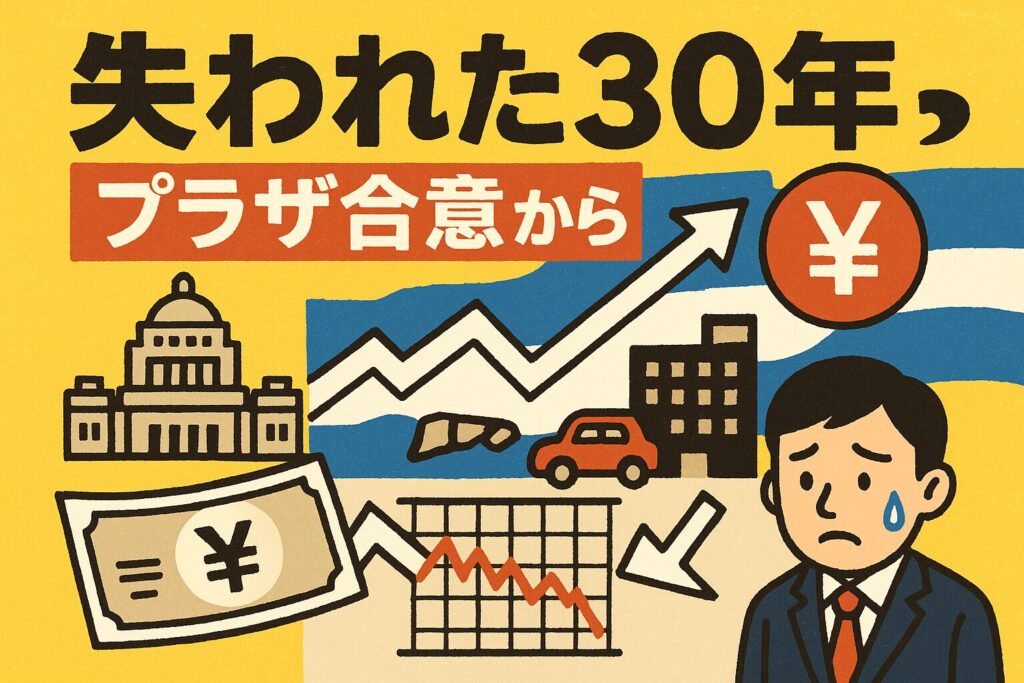
1980年代、日本は世界がうらやむほど絶好調でした。
でも、たったひとつの国際合意をきっかけに流れは一変します。
急な円高、不動産バブル、そして崩壊…。
やがて日本は「失われた30年」と呼ばれる長い停滞へと入っていきました。
今回は、その始まりとなった「プラザ合意」と、その後の日本経済の流れをわかりやすく解説します。
 | 1985年の無条件降伏〜プラザ合意とバブル〜【電子書籍】[ 岡本勉 ] 価格:902円 |
1985年:ドル安・円高のスタート
1980年代前半、アメリカは世界一の経済大国でありながら、深刻な「貿易赤字」に苦しんでいました。
簡単にいうと「輸入(外国からの買い物)が多すぎて、輸出(自国の商品を売る)が少なすぎる」状態です。
特に、日本や西ドイツから車や家電などを大量に買っていたため、アメリカの国内産業(自動車・鉄鋼など)は大きな打撃を受けていました。アメリカの工場は閉鎖、失業者も増加し、「これはなんとかしないと!」という危機感が高まっていたのです。
そこで1985年9月、アメリカ・日本・西ドイツ・フランス・イギリスの5か国(G5)がニューヨークのプラザホテルに集まり、ある決定をしました。
それが「ドルの価値を下げよう!」という国際協調――プラザ合意です。
ドルの価値が下がれば、相対的に日本円やマルク(ドイツの通貨)の価値は上がります。
この仕組みを利用して、アメリカの輸出を増やし、逆に輸入を減らして、赤字を減らそうと考えたのです。
結果、わずか2年間でドルは急落し、1ドル=240円台だった為替が、なんと120円台まで半分近くに!
つまり、日本円の価値は急激に「円高」になったのです。
円の価値が上がるとどうなるでしょう?
- 日本の商品は「海外で高すぎて買えない」ものになってしまう
- 車や電化製品など、日本の輸出産業は一気に売れなくなる
- 日本企業は「円高不況」と呼ばれる大きな打撃を受ける
こうして、日本は輸出主導の経済モデルが揺らぎ、先の不況へとつながっていきました。
景気対策が「バブル」に
プラザ合意のあと、日本は急激な円高に見舞われ、輸出が落ち込んでしまいました。
「このままじゃ企業が倒産してしまう!」と焦った日本政府と日銀は、景気を下支えするために思い切った対策をとります。
それが 「超低金利政策」 です。
金利を下げると、銀行からお金を借りやすくなります。
企業は投資や事業拡大のためにお金を借りやすくなり、個人も住宅ローンなどで気軽に借金できるようになります。
本来なら、この政策によって「設備投資が増える」「給料も上がる」「消費が活発になる」という好循環を期待していました。
ところが実際には、余ったお金が 株式市場や不動産市場 に流れ込んでいきます。
銀行も「土地担保なら絶対安全!」と考え、どんどん融資をしてしまいました。
その結果、株価や土地価格はみるみるうちに上昇。
「土地は永遠に値下がりしない」「東京の地価でアメリカ全部が買える」なんて言葉まで飛び交うほどの異常な高騰ぶりでした。
こうして日本経済は、実体以上にお金が膨れ上がった「バブル経済」へと突入していったのです。
1989年:バブル崩壊のはじまり
株や土地の値段がぐんぐん上がり続けたバブル期。
しかし、「これはさすがに異常だ」と感じた日銀は、1989年から方針を大きく転換します。
それが 金利の引き上げ です。
金利が上がると、お金を借りるのが難しくなります。
すると株や土地を買う人が減り、需要が冷え込んで価格は下がり始めます。
最初は「ちょっとの調整」で済むと思われていました。
でも実際には、値上がりを前提に投資していた人たちが一斉に売りに走り、株価も地価も一気に暴落してしまいました。
ここで大問題になったのが 銀行の融資 です。
バブル期、銀行は「土地は絶対に値下がりしない」と信じて、企業や個人に多額のお金を貸していました。
しかし土地の価格が急落したことで担保の価値はなくなり、返済が滞る借金が大量に発生。
これを 不良債権 と呼びます。
銀行は資金繰りに苦しみ、今度は「もう貸せません!」と貸し渋りを始めます。
お金を借りられなくなった企業は次々に倒産。
経済全体が一気に冷え込む、まさに「バブル崩壊」の時代が訪れたのです。
補足
① なぜ日銀が金利を上げたのか?
バブル期は、株や土地の値段が毎年ものすごい勢いで上がっていました。
でもこれは「実力以上の値上がり」で、投資バブルに近い状態。
そこで日銀は
- お金が出回りすぎている(金融緩和しすぎ)
- このまま放っておくと危険(過熱しすぎ)
と判断して、「ブレーキ」をかけるために 金利を引き上げた のです。
金利を上げるとお金を借りにくくなり、株や土地を買う人が減って価格の上昇が止まる狙いがありました。
② 不良債権とは何か?
「不良債権(ふりょうさいけん)」は、簡単に言うと 銀行が貸したのに返ってこないお金 のことです。
バブル期、銀行は「土地は絶対に値下がりしない!」と信じて、どんどん企業や個人に融資しました。
でも土地や株の価格が暴落すると、担保の価値もなくなり、借り手は返済できなくなりました。
結果、銀行には「貸したけど回収できない借金」が大量に残り、それが 不良債権 です。
銀行はこの処理に追われて新たにお金を貸せなくなり、経済全体が冷え込む原因となりました。
👉 この2つをまとめると、
- 金利引き上げは「バブルの熱を冷ますための処置」だった
- でもその副作用で暴落が一気に進み、「不良債権問題」が日本経済を長期停滞に追い込んだ
という流れになります。
その後の日本:長い不況とデフレの時代
バブル崩壊の衝撃は、日本経済に 深い傷跡 を残しました。
土地や株が暴落し、銀行は不良債権という 「回収できない借金の山」 を抱えます。
銀行がお金を貸せなくなると、企業は資金不足で設備投資や新規事業ができなくなり、給料も上がらず消費も冷え込みます。
これが連鎖的に起こり、経済全体の元気がどんどん失われていったのです。
さらに物価まで下がる デフレ が発生しました。
物が売れない → 企業の売上が減る → 給料が上がらない → 物が売れない…という悪循環が続きます。
まさに経済全体が「冬の時代」に入ったような状況です。
こうして1990年代は 「失われた10年」 と呼ばれました。
しかし不況は短期間で終わらず、企業も国民もなかなか立ち直れず、結局 「失われた30年」 とまで言われる長い停滞期に突入してしまったのです。
まとめ:プラザ合意から失われた30年まで
日本の経済が長期停滞に陥った流れを、ざっくり言うとこんな感じです👇
- プラザ合意(1985年)
アメリカ主導で「ドル高すぎるから下げよう!」と決まる。 - 円高不況
円の価値が急上昇。日本の輸出産業が打撃を受け、車や電化製品が海外で売れにくくなる。 - 金利下げ(景気対策)
お金を借りやすくして国内景気を支える政策。 - バブル発生
余ったお金が株や土地に流れ込み、価格が異常に上昇。いわゆるバブル経済へ。 - バブル崩壊(1989年~)
日銀が金利を上げたことで株価・地価が暴落。 - 不良債権・デフレ
銀行は回収できないお金(不良債権)を抱え、貸し渋りが発生。企業倒産や給料下落で消費も冷え込む。 - 失われた30年
景気はなかなか回復せず、長期停滞期に突入。物価も上がらないデフレ状態が続く。
たった一つの国際会議の決定が、日本経済に 大きな歴史的転換点 をもたらしたんですね。
希望なら、この流れを 図解やタイムライン形式 にして、ブログ読者が一目で理解できるようにすることもできます。
作ってほしいですか?
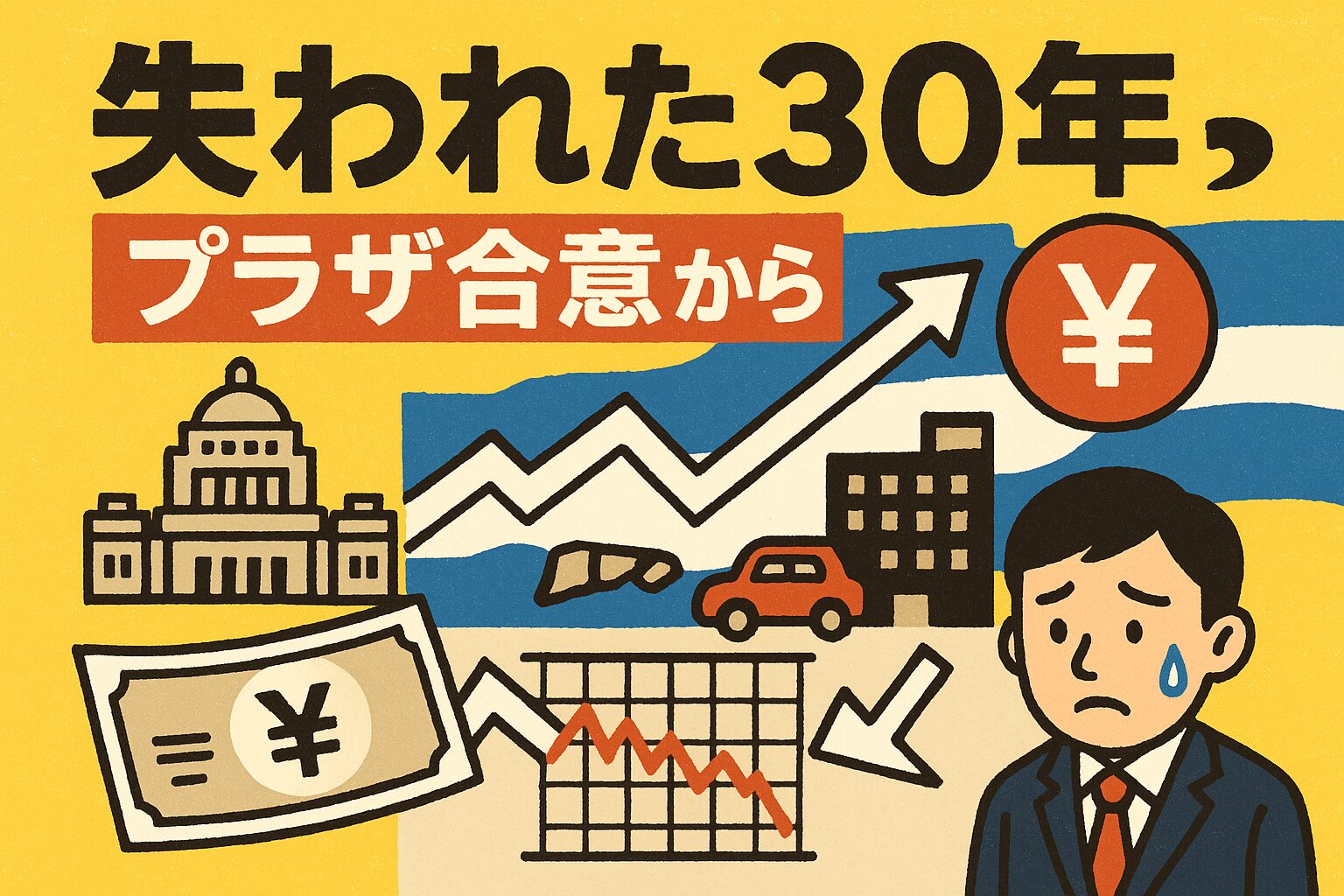


コメント