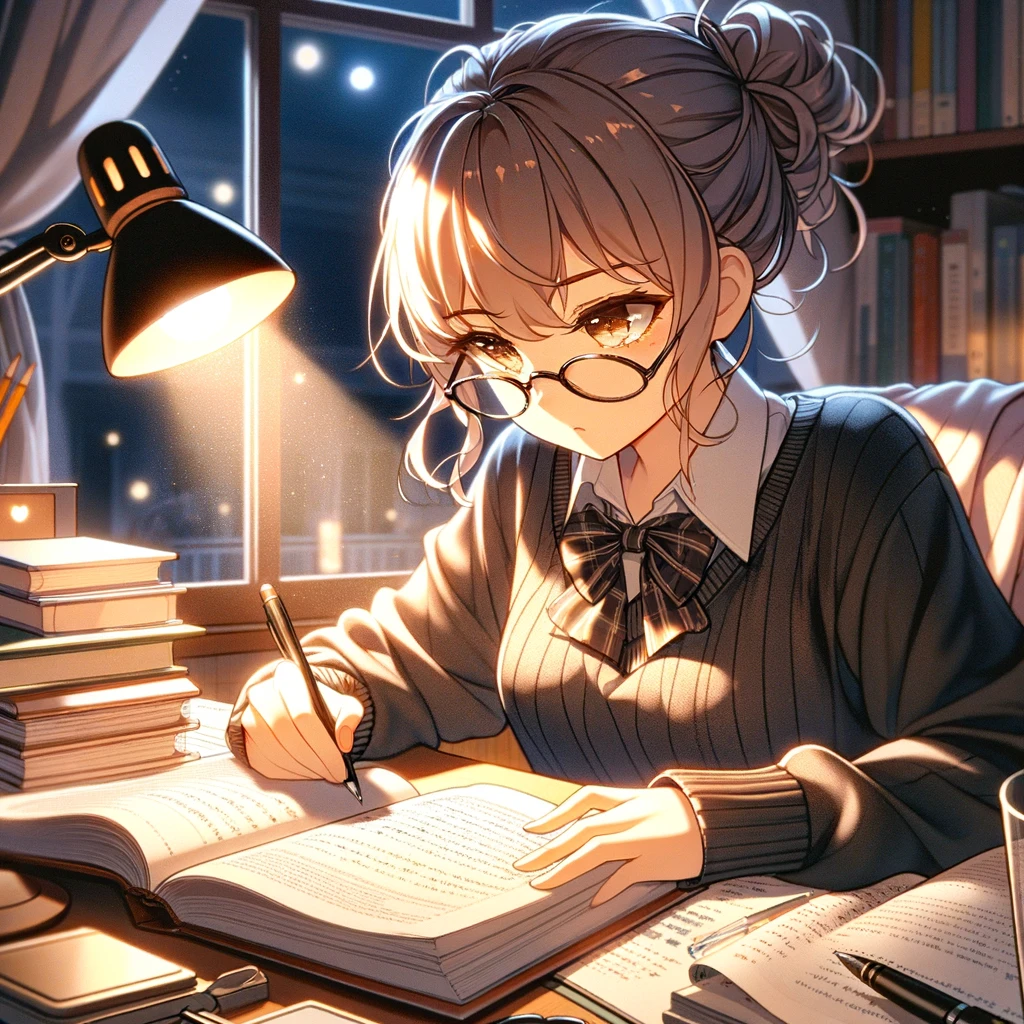
皆さんは学校で過ごした長い時間を振り返り、時に「これらの勉強が将来に役立つのだろうか?」と疑問に思ったことはないでしょうか。数学の公式、歴史の年表、文学の解釈…これらが社会で直接役立つ場面はそう多くありません。多くの人が、学校での勉強が実生活で役に立たないと感じ、疑問を抱いています。しかし、福沢諭吉、日本の近代化を牽引した思想家兼教育者は、学問の重要性について、私たちが見落としがちな別の視点を提供しています。
福沢諭吉は「勉強しない者は、いつも勉強する者に騙される」という言葉で、学ぶことの本質的価値を強調しました。彼の見解では、学問は単に知識を蓄えること以上の意味を持ちます。それは自ら考え、判断する力、つまり「主体性」を養うことです。この能力は、社会で自立して生きるために不可欠なものです。
例えば、歴史を学ぶことで、過去の成功と失敗から教訓を得ることができます。これにより、自分自身で物事の良し悪しを判断できるようになります。また、数学を学ぶことで、数字に強くなり、複雑な計算や経済的な判断ができるようになります。これは、日常生活やビジネスの場で騙されることを減らし、賢い決断を下すのに役立ちます。
福沢諭吉は、学びを通じて得られる「判断力」が、人を騙そうとする情報が氾濫する現代社会において、いかに重要かを説きました。真実を見極める力は、情報に溢れる時代を生きる私たちにとって、かけがえのないものです。学問を通じて磨かれるこの力は、社会で自立し、成功するための基盤となります。
この記事では、福沢諭吉の「勉強しない者は、いつも勉強する者に騙される」という言葉を深掘りし、学びが個人の成長や社会での成功にどのように貢献するかを具体的に探求します。学問が私たちに主体性を与え、真実と嘘を見分ける力を養う方法について考えてみましょう。
 | 福沢諭吉「学問のすすめ」 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫) [ 福沢 諭吉 ] 価格:733円 |
福沢諭吉という男
まずは、福沢諭吉について解説します。彼は現在の1万円札の肖像画で知られており、名前を聞かない人は少ないでしょう。しかし、実際に彼が何を成し遂げた人物なのかを詳しく知る人はそれほど多くないかもしれません。福沢諭吉は、明治時代に自由と平等の価値、そして学問の重要性を広めた重要な人物です。彼は現在の大分県豊前市中津藩の下級武士の家に生まれました。福沢が生まれた2年後、父は45歳の若さで亡くなり、家は貧しい生活を余儀なくされました。幼い頃から、諭吉は母の内職を手伝い、下駄の修理や畳の張り替えなど、何でも自分で調べて、自分で考えればできると信じ、自立心を育んでいました。彼は「自分でよく見て、自分でよく考えれば、何でも自分でできる。自分でやればお金はかからない」という信念を持っていました。
14歳で塾に通い始めた諭吉は、読み書きを覚えるとすぐに地域で一番の学力を身につけました。この頃から、彼はもっと勉強したく、社会的な成功を手に入れたいと考えるようになります。しかし、そんな彼を良く思わない周りの武士からは、「下級武士の分際で何を生意気に。お前は上級武士に従っていればいい。下級武士は一生下級武士だ」といった反発を受けました。当時の日本は、人の能力よりも身分が人の価値を決める、非常に閉鎖的な社会でした。
18歳の時、ペリーによる黒船来航とそれに伴う国境の開放が、諭吉にとって大きなチャンスとなります。日本が約210年間続いた鎖国を終え、国として西洋文化を学ぶ必要が生まれたのです。これを機に、諭吉は長崎に行き、オランダ語及びオランダ文化を学び始めます。約4年間の勉強の後、外国人が多く住む横浜に向かいましたが、そこで彼は、自分がマスターしたオランダ語がほとんど通用しないこと、当時の国際標準が英語であることを知ります。しかし、彼は決して諦めず、独学で英語を学び始めました。
その後、1860年に日本がアメリカに遣使団を送ることになり、諭吉はその一員として選ばれます。アメリカで身分制度のない自由な社会や、西洋の進んだ文化・技術に衝撃を受け、イギリスやオランダ、ドイツ、ロシアを訪れ、各国の政治や文化を学びます。彼は日本ももっと海外との関わりを持ち、進んだ知識を学んでいかなければ、国際社会で遅れを取ってしまうと感じました。
しかし、このような国際感覚を持つ諭吉とは裏腹に、多くの日本人は古い考えに囚われており、政府も外国の圧力に屈すると信じていました。そこで諭吉は、日本人にもっと海外の情報を知らせなければならないと考え、「西洋事情」という書籍を出版し、欧米の文化や政治倫理を紹介しました。これにより、日本がいかに国際社会に遅れているかを人々に理解させ、文明開化を進めました。
明治天皇による幕府の廃止と明治維新の後、諭吉は新政府から官職への就任を求められましたが、彼はそれを断り、教育者としての道を選びました。なぜなら、彼は日本が西洋諸国と対等に渡り合うためには、国民一人ひとりがもっと学び、自分で物事を判断できるようになる必要があると考えていたからです。そこで、彼は人々が学ぶために、現在の慶應義塾大学の前身となる慶應義塾を創設しました。その後、1872年には「学問のすすめ」を発表し、これが当時の人口約3400万人のうち1人に1冊の割合で読まれたと言われています。
なぜ人々が学問を学ぶべきなのか?
福沢諭吉は、なぜ人々が学問を学ぶべきだと考えたのかについて、このように述べています。「人は自由になるために学問を学ばなければならない。そうでなければ、誰かに依存して生きることになり、自由を失い、簡単に騙されることになる。」つまり、福沢諭吉は学問を通じて獲得される自立と批判的思考の能力が、人々を自由にし、他者による搾取や騙しに対する防御手段となると主張していました。
学問が社会でどのように役立つのか疑問に思う人もいるかもしれません。もし学校の勉強が役立っていないと感じるのであれば、それは周りの意見に流され、自分で考えることを放棄している証拠かもしれません。周りに依存し、他人がやっていることをただ真似るだけでは、自分自身の判断や選択を放棄することになります。その結果、もし周囲が間違った方向に進んだ場合、自分も同じ過ちを犯すことになります。これは、まさに自分自身で新しい道を選びたいときに、何が正しいかを知らず、自由を失ってしまう状況です。
例えば、国語の授業で適当に過ごし、正確な言語能力を身につけなければ、広告などの言葉の罠に簡単に騙されてしまいます。たとえば、ある家電量販店の広告に「同額保証。他店のチラシをお持ちいただければ、その価格まで値引きします」と書かれている場合、この広告の意図を正しく理解する能力がなければ、真実と異なる誤解を生じ、不利な取引をしてしまう可能性があります。実際には、このような広告戦略は、価格競争を避け、顧客を店に引きつけるためのものですが、批判的に考え、正確な情報を把握する能力がなければ、表面的なメッセージに騙されがちです。
言い換えれば、勉強をしなければ、学んだ人に搾取される側に立つしかなくなるのです。福沢諭吉は、学問を通じて獲得する知識と批判的思考能力が、私たちを本当の意味で自由にし、社会で自立して生きるための重要な基盤であると信じていました。
歴史を学ぶ重要性
自分で歴史を学ばないと、信憑性が疑わしいネット上の記事を鵜呑みにし、それを事実だと誤信してしまうリスクがあります。TwitterやYahoo!知恵袋のようなプラットフォームで聞いたこと、そこで見つけた無名の人物の回答を事実として受け入れがちです。同様に、服装について学ばなければ、友人の言葉から「黒パンツは流行っていない」という根拠のない情報を真に受けてしまうかもしれません。政治について学ぼうとしないと、多くの人が何を考えているかに頼り、その意見を無批判に信じ、十分な知識もなしに政治を批判する人が生まれてしまいます。哲学を自分で学ばなければ、特定のチャンネルの情報が全て虚偽であっても、その真偽を見抜くことができなくなります。
つまり、真実か虚偽かを自分で判断するためには、学問を学ぶ必要があります。学問を学ばずに人に依存し、無批判に他人の意見を信じ込むことになれば、自由を得ることはできません。福沢諭吉は、自由になるためには自分で学び、自分で考えることの重要性を説きました。これは、自分の頭で考え、情報の真偽を判断できる力を身につけることが、自由への道であるという彼の考えを反映しています。情報があふれる現代社会において、このメッセージはより一層の重要性を帯びています。自分で学び、自分で考えることは、情報に振り回されずに生きるための基礎となります。
自由
福沢諭吉は「自由」という概念を、自己の独立として定義しました。彼にとって、自由とは自分の人生に対する全責任を自分自身で担うこと、自分の行動とその結果に自分で責任を持つことです。このような自立した生き方を実現するためには、学問を通じて自己を養うことが不可欠だと彼は主張します。独立者とは、他人に依存することなく、他者の意見に左右されずに自分の判断で行動し、その結果に対して自分で責任を取る人のことを指します。これこそが真の自由、そして人間の理想的な姿であると福沢は説いています。
例えば、SNSなどで見られる「自分の給料が少ないのは国のせい」「仕事が辛いのは上司の責任」「生活が苦しいのは家族のせい」といった発言は、問題の根源を他者に転嫁する行為です。これらは、自分の問題を自分で解決する能力がないことの表れであり、本質的には自分以外の何かに依存している状態を示しています。福沢は、もし国の政策に納得がいかないなら、自分が政治を学び、政治家になるなどの行動を取るべきだと提案します。また、仕事が辛い場合には、転職を含む様々な選択肢を自分で模索すべきだと説きます。
このように、不満や問題は依存することから生じると福沢は指摘しています。何かに依存すると、他人に頼る人間になりがちで、自分自身で何とかしようとする主体性が失われてしまいます。その結果、自分で物事を判断する力を失い、他人を批判することしかできなくなってしまうのです。福沢諭吉の考える自由は、自分の人生を自分で切り開く力と責任感を持ち、学問を通じてその能力を養うことにあります。これは単に自己責任を強調するだけでなく、自分自身の可能性を最大限に引き出すための方法として学問の重要性を訴えています。
判断力
福沢諭吉は、個人の独立において判断力を身につけることの重要性を説いています。しかし、これを単純に「自分の頭で考えろ」という意味に受け取るのではなく、より深い学びと理解を推奨していました。彼が伝えたかったのは、単に自分で考えることの重要性を説くだけでなく、多くの本を読み、多くの物事に接して、潜在的な感覚を養いながら観察することにより、信じることと疑うことのバランスを見つけるべきだということです。
福沢諭吉は、自分で考えることは良いことだが、それだけでは不十分であり、その時点での既存の知識に基づいて考えるだけだと主張しています。つまり、自分の意見を形成することよりも、まずは学ぶことがはるかに重要だと言っています。その理由は、自分で考えるとは、その時に持っている知識に限定された考えをすることであり、多くの場合、その考えは既に誰かが試みて答えを出しているものだからです。
たとえば、数学で三角形の内角の和を知らない人が、自分で角度を計算しようとしても、ほとんどの場合間違った答えに終わるでしょう。この例からもわかるように、まずは学ぶことが重要であり、自分が納得できなければ、自分で詳しく調べ、検証し、納得できるまで勉強を続けることが、本当の学びであると福沢諭吉は述べています。
自分の頭で考えるためには、まず必要な情報を得て、それから考える必要があります。経験豊富で、研究を重ねてきた人々の結論を、初めは正しいものとして扱い、納得できなければ、自分が間違っている可能性を疑い、さらに納得できなければ、自分で勉強を深めることが大切です。このプロセスを通じて、自分だけの都合のいい情報に偏らずに、より正確で信頼できる知識を身につけることができると福沢諭吉は教えています。
人望の大切さ
福沢諭吉は、人が何かを成し遂げるためには人望が必要であり、その人望を獲得するためには知性が不可欠であると述べました。例えば、知識が自分より少ない上司を見たときや、勉強ができない息子を一人暮らしで心配するときなど、私たちは知性の有無に基づいて信頼や尊敬の感情を持ちます。人々は知性ある行動や判断を尊重し、そのような人物に自然と引かれます。言い換えれば、知性を持っていれば、積極的に人脈を築く努力をしなくても、人は自然と信用し、関わりたがるようになると彼は考えました。
この知性は、可愛らしさや愛嬌とは異なり、努力によって習得可能なものです。そのため、福沢諭吉は学びを通じて得られる知性を非常に重要視しました。現代社会では「常識を疑え」や「自分で考えろ」とよく言われますが、彼は、学ぶ気がなければ、疑わずに周りに合わせる方が賢明だと考えていました。結婚や学歴などの社会的な常識に対して懐疑的な意見が増えていますが、彼はそうした意見に流されず、自分自身でしっかりと学び、疑問を持つことの重要性を強調しました。
彼の言葉を現代に当てはめると、陰謀論やSNS上の怪しい情報に騙されないためにも、自分でしっかりと学び、物事を深く理解する必要があるということです。常識に疑問を感じることは大切ですが、その前に自分の理解が正しいかどうか、まずは疑うべきです。偉人の教えや社会の常識に違和感を覚えたとしても、その理由を深く探求し、自分の知識や理解を深めることが、真の学問への道となります。福沢諭吉は、このように自己の知性を磨き、広い視野で物事を捉えることの大切さを説いています。


コメント