
2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞したのは、日本の免疫学者・坂口志文(さかぐち しもん)氏でした。
彼が発見したのは、私たちの体を守る免疫システムの中で“暴走を止めるブレーキ”の役割を果たす細胞、「制御性T細胞(Treg)」です。
通常、免疫はウイルスや細菌など外敵を攻撃して健康を守る仕組みです。しかし、この攻撃のスイッチが切れなくなると、自分の体を攻撃してしまう――いわゆる自己免疫疾患が起こります。坂口氏は「免疫には攻撃だけでなく、静める力もある」と世界に示し、医学の常識を根本から変えました。
この発見によって、関節リウマチや1型糖尿病、アレルギー、移植医療、さらにはがん治療や再生医療にまで新しい道が開かれようとしています。免疫を“抑える”ことで病気を治す――そんな逆転の発想を現実にしたのが、坂口氏の研究なのです。
本記事では、「制御性T細胞とは何か」「どんな病気に応用できるのか」「これから医療がどう変わるのか」を、専門知識のない人でも理解できるよう、やさしく丁寧に解説していきます。
坂口志文氏のノーベル賞への道
坂口志文(さかぐち しもん)氏は、1951年に滋賀県長浜市で生まれた日本の免疫学者です。2025年にノーベル生理学・医学賞を受賞し、世界中から注目を集めました。彼は、人間の免疫システムの中に「過剰な反応を抑える仕組み=制御性T細胞(Treg)」が存在することを発見したことで知られています。
医学の道を志した若き日
坂口氏は京都大学医学部を卒業し、同大学で医学博士号を取得しました。医師としてではなく、「病気の原因を根本から解き明かしたい」という思いから研究者の道を選びます。学生時代から「免疫とは何か」という問いに強く惹かれ、体の中で起こる複雑な免疫反応の仕組みを理解しようと情熱を注いでいました。
海外での挑戦:アメリカでの研究生活
1980年代、坂口氏はアメリカの名門・ジョンズ・ホプキンス大学などでポスドク(博士研究員)として研究を行いました。
この時期は、免疫学が大きく発展し始めたタイミングで、世界中の研究者が免疫細胞の働きを解明しようと競っていた時代です。坂口氏は国際的な研究環境の中で、免疫の複雑さと奥深さに直に触れ、その後の発見につながる「免疫のバランス」という発想を深めていきました。
日本へ帰国後の歩み:大阪大学での研究
帰国後は、京都大学や大阪大学などの研究機関で免疫学の研究を続けました。現在は、大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC)の特任教授として活動しています。
このセンターは、日本でもトップレベルの免疫研究拠点で、坂口氏のような世界的研究者が集まる場所です。ここで彼は若い研究者たちの育成にも力を入れ、国際的な免疫研究の中心的存在として活躍しています。
ノーベル賞受賞:世界が認めた「免疫のブレーキ」の発見
2025年10月6日、坂口志文氏は米国のメアリー・ブランコウ氏、フレッド・ラムズデル氏とともに、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
受賞理由は、「免疫応答を抑制する制御性T細胞の発見」。これは、人類の病気の理解と治療法を根本から変える発見とされています。
免疫は“敵を攻撃するシステム”だと思われてきましたが、坂口氏は“攻撃を止めるシステム”も存在することを証明しました。これにより、自己免疫疾患・アレルギー・臓器移植など、幅広い分野で新しい治療の道が開かれたのです。
信念で切り開いた研究者人生
坂口氏の研究は、最初のころは多くの学者から「そんな細胞が本当にあるのか?」と疑われていました。しかし、彼は確かなデータと論理を積み重ね、「免疫にはブレーキがある」という事実を実証していきました。
長い年月をかけて信念を貫いた姿勢は、今や多くの研究者に勇気を与えています。
坂口志文氏は、滋賀の小さな町から世界の科学界に大きな足跡を残した研究者です。
彼の発見は、単なる医学の進歩にとどまらず、「人間の体は攻撃だけでなく、調和と制御によって守られている」という深いメッセージを私たちに教えてくれます。
坂口氏の歩みは、科学への探究心とあきらめない信念が、どんな困難も乗り越える力になることを示す、まさに現代科学の希望の物語です。
🧬 1. 研究の背景:なぜ“免疫のブレーキ”が必要なのか?
私たちの体には、ウイルスや細菌などの外敵を攻撃して守る「免疫システム」があります。
この免疫は非常に強力で、体を守るために毎日活発に働いています。
しかし、この免疫の力が暴走してしまうと、今度は「自分自身の体」を敵と勘違いして攻撃してしまうことがあります。
これが「自己免疫疾患」と呼ばれる病気です。
(例:関節リウマチ、1型糖尿病、橋本病、潰瘍性大腸炎など)
もともと、免疫が自分を攻撃しないようにする仕組みとして知られていたのが「中心性免疫寛容(central tolerance)」です。
これは、免疫細胞が胸腺(きょうせん)という臓器で“教育”されている間に、「自分を攻撃する細胞」を排除してしまう仕組みのことです。
ただし、これだけでは十分ではありませんでした。
教育の段階を通り抜けた後にも、“誤作動”を起こす免疫細胞が存在することが分かってきたのです。
ここで登場するのが、坂口志文氏が発見した「制御性T細胞(Treg)」です。
 | <メール便1個まで可能>DEMECAL(デメカル)血液検査キット 生活習慣病+糖尿病セルフチェック【検査セット・郵送検査・自己採血・簡単検査・セルフ検査】【母の日・父の日・生活習慣病セルフチェック】 価格:7480円 |
🧩 2. 坂口氏の発見:制御性T細胞(Treg)とは?
坂口氏は1990年代、京都大学での研究の中で、免疫反応を抑える特別なT細胞の存在を見つけました。
それが「制御性T細胞(Regulatory T cell, Treg)」です。
Tregは、他の免疫細胞(たとえば攻撃型のT細胞)が暴走しないようにブレーキをかける役割を持っています。
つまり、免疫システムの中で「攻撃する側(アクセル)」と「止める側(ブレーキ)」の両方が存在し、バランスを取っているということを初めて示したのです。
坂口氏の発見によって、免疫は単なる“戦うシステム”ではなく、攻撃と抑制のバランスで成り立っていることが明らかになりました。
🧠 3. 共同研究:FOXP3遺伝子の発見とのつながり
坂口氏の発見の後、アメリカの研究者 メアリー・ブランコウ氏 と フレッド・ラムズデル氏 が、Tregの機能を決定づける遺伝子を探していました。
彼らは2001年に、マウスの中で「FOXP3(フォックスP3)」という遺伝子が壊れると、免疫のブレーキが効かなくなり、体中で自己免疫反応が起こることを突き止めました。
さらに、人間でもこの遺伝子に異常があると「IPEX症候群」という重い自己免疫病になることがわかりました。
坂口氏もこの研究を発展させ、FOXP3がTregの“司令塔”のような遺伝子であり、これがTregの性質を決める“マスター遺伝子”であることを明らかにしました。
つまり、
🧩 坂口氏 → Tregという細胞を発見
🧬 ブランコウ氏・ラムズデル氏 → その中核となるFOXP3遺伝子を発見
この連携によって、免疫の制御メカニズムの全体像がつながったのです。
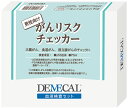 | 価格:13200円 |
🌿 4. 「末梢免疫寛容」とは?
ここで出てくる「末梢免疫寛容(peripheral immune tolerance)」とは、
胸腺での教育(中心性寛容)を終えたあと、成熟した免疫細胞を外の現場で制御する仕組みのことです。
つまり、免疫システムは二重の安全装置を持っています。
1️⃣ 胸腺で“危ない免疫細胞”を育てない(中心性寛容)
2️⃣ それでも漏れたものを、Tregが現場で止める(末梢寛容)
この発見によって、免疫の安全機構の「最終防衛ライン」がどこにあるのかが明らかになったのです。
 | 【第2類医薬品】アレジオン20 (24錠)(24錠*2コセット(セルフメディケーション税制対象))【アレジオン】[48日分 1日1回 花粉 アレルギー 鼻炎 眠くなりにくい] 価格:4031円 |
💡 5. この発見がもたらす医療への応用
坂口氏の研究は、今後の医療を大きく変える可能性を持っています。
✅ 自己免疫疾患の治療
Tregを増やしたり強化することで、体の“誤作動”を抑え、関節リウマチや1型糖尿病などの治療に応用できます。
✅ がん免疫療法
逆に、がん細胞の周りでTregが多すぎると、免疫ががんを攻撃できなくなります。
Tregの働きを一時的に“外す”ことで、がんへの免疫攻撃を強める治療法の開発が進んでいます。
✅ 臓器移植やアレルギー治療
Tregを活用すれば、移植した臓器を体が拒絶しないようにしたり、アレルギー反応を和らげる治療にも役立つと期待されています。
 | <メール便1個まで可能>DEMECAL(デメカル)血液検査キットメタボリックシンドローム&生活習慣病セルフチェック【検査セット・郵送検査・自己採血・簡単検査・セルフ検査】【母の日・父の日・敬老の日】 価格:7257円 |
🏆 6. ノーベル賞の評価
ノーベル委員会は、坂口氏らの発見を
「免疫システムが外敵と戦いながら、自分自身を攻撃しないようにする仕組みを明らかにした」
と高く評価しました。
免疫の“アクセルとブレーキ”のバランスを理解することは、人類の医療に新しい時代を開く発見だったのです。
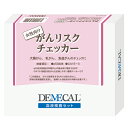 | 価格:10758円 |
🔍まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発見者 | 坂口志文氏(制御性T細胞の発見) |
| 共同受賞者 | メアリー・ブランコウ氏、フレッド・ラムズデル氏(FOXP3遺伝子の発見) |
| 仕組み | 免疫の暴走を防ぐ「末梢免疫寛容」 |
| 意義 | 自己免疫・がん・移植などの治療に新しい可能性 |
| 受賞理由 | 「免疫の制御メカニズムの発見による人類への貢献」 |



コメント