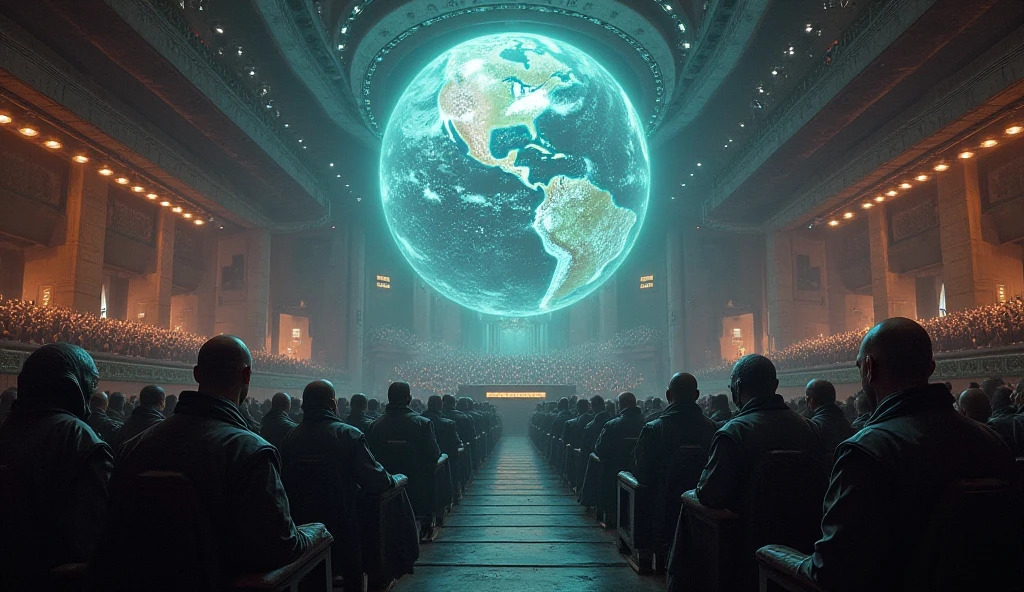
アメリカの調査会社ユーラシアグループが、2025年の世界重大リスクを発表しました。ユーラシアグループは、国際政治学者のイアン・ブレマー氏が社長を務める会社で、1998年からその年の政治や経済に大きな影響を与える地政学リスクを予測してきました。
この地政学リスクとは、ある国や地域が持つ地理的な特徴が政治・経済・軍事的な問題と絡み合うことで、世界に与えるリスクのことです。例えば、原油産出地域で紛争が起こると原油価格が上がり、企業の生産活動や供給網が影響を受け、株価や金融市場の混乱を引き起こし、最終的には世界全体の経済に悪影響があるといったイメージです。
それでは、早速やっていきましょう。
10位 米国とメキシコの対立
10位は、「米国とメキシコの対立」です。
アメリカが保護主義を強化する一方で、メキシコがその圧力にどう対処するかによって、両国の関係が厳しく悪化する可能性が示されています。
まず、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、就任したばかりで国民からの大きな期待を背負っています。彼女は、国内の政治改革や経済課題にも取り組む姿勢を示しているところです。
しかし、2期目に返り咲いたトランプ大統領は、メキシコとの関係に対して厳しい姿勢を取っています。トランプ氏は選挙公約として、メキシコからの輸入品すべてに高い関税を課すとしています。その狙いは、不法移民問題やフェンタニルの密輸を抑止するためです。
また、メキシコ政府は輸出の大部分をアメリカに依存しています。もしアメリカが本当に高い関税を発動すれば、メキシコは輸出市場を失い、大きな経済的ダメージを受けることになります。メキシコ国内の企業や労働者、さらに家族に送金を行う在米メキシコ人など、多方面にわたって不利な状況が生じるでしょう。
そのため、シェインバウム大統領はアメリカの要求に部分的に譲歩してでも、高関税を回避したいと考えています。それでもアメリカは不法移民対策として、メキシコに強い圧力をかけています。
2025年1月21日には、難民申請者がアメリカの移民裁判所での審理が終わるまでメキシコに留まることを義務づける「メキシコ残留プログラム」の復活を発表しました。また、不法移民を裁判手続きまで釈放する「キャッチ・アンド・リリース」の慣行を廃止するという大統領令にも署名しました。
シェインバウム氏にとっては、政治的に極めて厳しい判断を迫られることになります。なぜなら、こうした政策には人道的な懸念もあり、さらに国民から「アメリカに屈している」と批判される可能性があるからです。
加えて、北米自由貿易協定(USMCA)の再交渉も大きな焦点となるでしょう。トランプ政権は貿易赤字を減らすために、メキシコとの合意内容をさらに厳しく見直そうとするかもしれません。特に自動車やエネルギー産業では、原産地規則の見直しや、メキシコ国内での労働基準・賃金水準などを厳しくチェックすることで、トランプ氏はアメリカに工場を移転させることを狙っているとされています。
こうした動きは、メキシコの経済や政治に大きな混乱をもたらします。これまでメキシコは、アメリカとの結びつきによって成長を続けてきました。しかし、もしここで米国との関係が悪化すれば、外国企業が投資を控えたり、国際的な信用が低下したりするリスクもあります。
国内の財政状況は厳しいため、政府は社会保障や公共事業に大きく予算を使う余地が限られており、長期的な経済発展が妨げられる可能性もあるのです。
メキシコを拠点に生産する企業も数多くあるため、米国との関係が悪化すれば、当然、世界の経済活動にも影響が出てきます。シェインバウム氏とトランプ氏、それぞれの事情がある中で、どのような折り合いをつけていくのかが今後の焦点となるでしょう。
9位 統治なき領域の拡大
9位は、「統治なき領域の拡大」です。
紛争や混乱の影響によって長期にわたり放置された地域が、世界各地で拡大しています。そうした地域では、国家や国際機関による支援が行き届かず、生活に不可欠な物資やサービスが大幅に不足しています。
しかしながら、アメリカやヨーロッパなどの主要国は、内向きの政策を選ぶ傾向が強まっています。
「Gゼロ(G0)」とも呼ばれるリーダー不在の時代に突入したことで、紛争地域や貧困地帯を支える取り組みは一層手薄になっているとされています。
この「Gゼロ」という概念は、2011年にイアン・ブレマー氏が提唱したものです。
国際社会が直面している大きな課題を解決へと導く、強力なリーダーや主導的な枠組みが見当たらず、世界の問題が取り残されたままになっている状況を指します。
かつては、アメリカやヨーロッパを中心とするG7などの枠組みが、一定のリーダーシップを発揮していました。または、アメリカと中国が競いながらも世界秩序を保つという構図も存在していました。
しかし今では、そうした大国や国際組織がうまくリードできず、多くの問題が未解決のまま放置されるケースが増えているのです。これこそが、Gゼロと呼ばれる状態です。
十分な救援がなければ、現地では犯罪組織や武装勢力が台頭し、一般市民の暮らしにもさらなる脅威をもたらすという悪循環が進んでいきます。この流れは、世界全体の安定や安全をも脅かす深刻な要因だと言えるでしょう。
例えば中東では、長引く戦闘や政治対立によって、統治機能が崩壊寸前の地域も珍しくありません。空爆や銃撃が絶えず、医療や食料といった基礎的な支援すらままならないケースもあり、現場の人々は疲弊しています。
さらにアフリカ・サヘル地帯でも、クーデターによる政情不安が増し、もともと脆弱だった統治が崩れかけています。こうした地域では社会の仕組みが機能しにくくなり、仕事や農業が壊滅的な打撃を受けることで、食料不足や感染症の拡大など、複合的な問題が顕著になってきています。
しかし、メディアの注目度も低いため、国際社会からの支援は後回しにされているのが現状です。
さらに、ウクライナの一部地域では、軍事衝突が続く中で「統治なき領域」が生まれるおそれがあります。仮にロシアとの停戦が成立したとしても、正式な和平まで至らなければ、住民の安全な暮らしの確保は宙ぶらりのままになりかねません。
本来であれば、こうした地域を支援し再建を後押しするためには、国際的な支えが欠かせません。しかし現状では、国際協調よりも外交的な対立が目立っており、それ自体がまた新たなリスクとなっています。
このように、統治なき領域が拡大すれば、テロや犯罪組織が根を下ろしやすくなります。すると、麻薬や武器の密売といった脅威が国境を超えて広がる可能性も高まります。
また、難民や移民が急増することで、社会的な混乱を招くこともありえます。
遠い場所での紛争や貧困だからといって無視していると、巡り巡って自国の安全や経済にまで影響を及ぼすかもしれないのです。
8位 制御不能なAI
8位は、「制御不能なAI(人工知能)」です。
AIの進化があまりにも急速に進んでおり、それに対応するためのルールや安全策が追いついていないため、意図せず大きな問題を引き起こすリスクが高まっていると言われています。
実際、AIの技術は驚くほどのスピードで発展しています。
大規模言語モデルのような仕組みを使えば、人間さながらに文章を作成したり、自然な会話を行ったりすることが可能になりました。
さらに、自律的に判断・行動するAIの研究も進められており、「AIがどのような振る舞いをするのか人間がもはや管理できなくなる」という可能性すら懸念されています。
高度なAIがさまざまな領域で使われるようになるほど、誤作動や悪用といったリスクも大きくなると指摘されています。
例えば、株式市場の取引を行うAIの判断で、かつてないような大暴落を引き起こすかもしれません。
あるいは、兵器システムに搭載されたAIが「最も合理的な判断」として、人間が意図しない攻撃をしてしまうおそれもあります。
さらに、フェイクニュースや偽映像を自動で作成・拡散するようなAIが台頭すれば、真偽を見分けるのがますます困難になります。
仮に選挙結果を左右するほどの情報操作が行われていたとしても、それに気づけない可能性が出てくるのです。
それがより高度化すれば、政治判断の誤りや不正にさえ気づけなくなるおそれもあります。
本来であれば、こうしたAIリスクに備えるために、国際的なルールやガイドラインを設け、安全に活用できる体制を整えておく必要があります。
しかし実際には、アメリカや中国などの大国間でAI開発競争が激化しており、国際協調は思うように進んでいません。
とりわけ、米中関係が緊迫している影響で、互いにAI技術を秘密裏に発展させようとする動きが強まり、透明性や安全策の共有が妨げられています。
その結果、誤った使い方や規制の抜け道が放置されたままになっているのです。
こうした「制御不能なAI」によるリスクは、経済的混乱や社会の分断、さらには軍事的な誤算など、幅広い問題を引き起こす懸念があります。
7位 世界経済への負の押し付け
7位は、「世界経済への負の押し付け」です。
アメリカと中国がそれぞれ自国の都合を最優先にする保護主義政策を強化することで、世界全体の経済に混乱と重荷をもたらすおそれがあると指摘されています。
まず、トランプ政権2期目では、大幅な関税の引き上げや不法移民の制限といった保護主義的な措置を強化し、自国産業を守ろうとしています。
たとえば、中国からの輸入品に非常に高い関税をかけることで、企業や消費者にアメリカ製を優先的に選ばせようとしているのです。
一方で、中国も対抗措置を取り、アメリカへの輸出を抑える傾向があります。
この結果、両国の貿易が停滞し、互いの景気回復が遅れるだけでなく、世界全体にも大きな影響を与えるリスクがあります。
さらに、中国は国内の経済成長が鈍化している中、輸出拡大によって自国の工場をフル稼働させようとする戦略を取ると見られています。
そうなると、安価な中国製品が一斉に他国へ流れ込み、地元企業が太刀打ちできなくなる国が出てくるかもしれません。
それに対応して各国も、自国の産業を保護するために高い関税をかける可能性があり、結果的に「関税合戦」が広がって、世界的に貿易が鈍化するおそれがあります。
また、アメリカの保護主義政策に関連して、インフレへの懸念から金利の高止まりが続くリスクも指摘されています。
金利が高いままだと、ドル建ての借金を持つ国々は返済が困難になり、特に発展途上国では財政負担が増して不安要因が大きくなります。
金融や貿易の混乱が広がると、景気後退をきっかけに政権への不支持が高まり、政治の不安定化を招く可能性があります。
実際、ブラジルやトルコといった新興国では、財政状況が悪化すると政治が不安定になり、通貨の価値が下落し、海外からの投資が逃げていくという悪循環が起こりやすくなっています。
つまり、アメリカと中国がそれぞれ保護主義を競い合うと、そのしわ寄せが「弾き出された側」に押し付けられることになり、世界経済全体がその影響を受けるのです。
6位 追い詰められたイラン
6位は、「追い詰められたイラン」です。
中東でさまざまな勢力が衝突する中、イラン自身も軍事面・政治面の両面で強い圧力にさらされている現状が指摘されています。
イランは長らく、シリアやレバノンの武装組織を支援することで、中東における影響力を確保してきました。
しかし、最近の情勢変化により、この戦略が行き詰まりを見せ始めています。
まず、イランにとっての大きな打撃は、代理勢力であるハマスやヒズボラの弱体化です。
ガザ地区のハマスはイスラエルの攻撃を受け、多大な損害を被りました。
レバノンのヒズボラも、重要な指導者や戦闘員を失い、さらにシリアのアサド政権も以前のような安定を保てていません。
イランはこれらの組織を裏側から支援することで、イスラエルやアメリカに対抗してきましたが、その優位性は大幅に損なわれています。
また、イランは核開発の分野でも大きなプレッシャーに直面しています。
イランの核兵器完成が間近に迫っていると見られており、「核をちらつかせれば攻め込まれにくくなる」というこれまでの抑止力戦略が、限界を迎えつつあります。
もし追い詰められたイランが本当に核武装に踏み切るようであれば、イスラエルやアメリカが先制攻撃を仕掛ける可能性も高まり、大規模な戦争に発展し、中東地域全体が大きく揺らぐ恐れがあります。
さらに、イラン国内にも深刻な課題があります。
国際的な経済制裁や政府の強権的な統治により、イランでは物価の高騰や失業率の上昇に苦しむ国民が多く、特に若い世代を中心に不満が高まっています。
もしイラン政府が軍事行動を拡大すれば、国民の暮らしはさらに悪化し、現体制への不満が一気に噴出するリスクも否めません。
アメリカのトランプ政権は、「最大限の圧力」をかける政策を復活させる大統領覚書に署名しました。
イラン産の原油が世界市場に出回らないように規制を強化し、中国などイランと取引を続ける国々にも圧力をかける方針を打ち出しています。
もしイランの収入源が断たれれば、経済的に行き詰まり、核開発を加速させたり、近隣諸国への挑発をエスカレートさせたりする懸念が一層高まります。
これは、イスラエルやアメリカが軍事行動に踏み切るきっかけを生み出す可能性もあり、衝突が起これば、石油やエネルギー関連施設に深刻なダメージが及び、原油価格は急騰し、経済・政治の安定が大きく損なわれることになるでしょう。
5位 ならず者国家のままのロシア
5位は、「ならず者国家のままのロシア」です。
ウクライナ侵攻や、北朝鮮・イランとの軍事協力などを通じて国際社会から孤立しつつも、反西側諸国としての立場を強めている点が指摘されています。
もともとロシアは、冷戦後に欧米側から迎え入れられる形で国際社会に参加しました。
しかし近年は欧米との対立が深まり、「ならず者国家(rogue state)」と呼ばれるほど強硬な姿勢を取るようになっています。
ウクライナへの軍事侵攻によって経済制裁を受け、人的資源や資金が流出しているにもかかわらず、ロシアは欧米に歩み寄る様子をほとんど見せてきませんでした。
2025年にはウクライナとの戦闘が一時的に停戦に向かうと見られています。
ただし、ロシア軍が実効支配している地域を既成事実化するだけであり、真の和平には至らない恐れがあります。
戦火が一時的に収まったとしても、ウクライナやNATO(北大西洋条約機構)との根本的な対立は解消されず、ヨーロッパ全域にわたる緊張は今後も残り続けるでしょう。
さらにロシアは、中国・イラン・北朝鮮といった「反西側」の国々との関係を深めています。
武器取引や軍事技術の交換を通じて、これらの国々のならず者的な行動を後押ししているとも言えます。
北朝鮮やイランの核・ミサイル開発が進めば、世界の安全保障は一層不安定になっていくでしょう。
これは、ヨーロッパから見ればエネルギー供給の混乱だけでなく、海底ケーブルの破壊やサイバー攻撃など、直接・間接を問わず強硬手段のリスクが増大することを意味します。
また、ロシアは新たな領土を求めて、ウクライナ侵攻で得た戦術を他の紛争地域でも繰り返す可能性があります。
このような動きが続けば、ヨーロッパだけでなく世界全体に不安が広がっていくことになるでしょう。
4位 トランプノミクス
4位は、「トランプノミクス」です。
トランプ大統領の2期目に実施されている経済政策は、アメリカ国内だけでなく、世界経済全体にも大きな影響を及ぼしています。
中でも、
① 関税の大幅引き上げ
② 不法移民の大量送還
という2つの政策が、さらなる混乱を引き起こすと指摘されています。
まず関税についてですが、トランプ氏はアメリカの雇用や産業を守るため、海外からの輸入品に高い関税をかけるという主張を一貫して続けてきました。
最大の標的は中国であり、中国製品には最大60%もの高関税をかけるというシナリオまで浮上しています。
さらに、2025年の終わりまでに、すべての国の輸入品に対して25%の関税を一律で課す可能性も示唆されています。
こうした保護主義的な政策が実施されれば、アメリカの企業や消費者にとっても輸入品のコストが高騰し、インフレが再び加速するリスクがあります。
次に、不法移民の大量送還です。
トランプ氏は1期目から不法移民対策を厳格化してきましたが、2期目ではさらに強硬な対応を取ると見られています。
数百万人規模の移民を強制送還するという方針は、農業・建設業・サービス業など、移民労働者に依存している産業に大きな打撃を与える可能性があります。
その結果、労働力の不足による人件費の高騰、生産性の低下が起こり、物価上昇や経済成長の鈍化を招くおそれがあります。
さらにトランプ氏は、金融・IT・環境分野などの規制を大幅に緩和・撤廃し、国内企業の活性化を図ると見られています。
しかし、アメリカの財政赤字や債務が膨らむ中で、減税や大型支出を続けていけば、金利やインフレのコントロールが難しくなるリスクもあります。
このように、「トランプノミクス」は保護主義・移民対策・規制緩和を柱とし、アメリカ国内の経済を刺激する政策です。
これは彼の選挙戦時代から一貫した主張であり、今回も主要な公約の多くが早期かつ大胆に実行され、世界中の経済関係者が動揺しています。
そして、それだけではありません。
トランプ氏の政治スタイル、「何をするか分からない」という個人的な性質そのものが、世界経済へのリスクとみなされているのです。
3位 米中決裂
3位は、「米中決裂」です。
アメリカと中国がこれまで以上に強く衝突し、世界的な安定を大きく揺るがす危険性が高まっていると指摘されています。
トランプ氏は2期目に入るとすぐに、中国からの輸入品に10%の追加関税を課す大統領令に署名しました。
これは、以前から懸念されていた50〜60%の高関税導入に向けた「第一段階」と見られています。
これに対し、中国側もアメリカからの輸入を制限したり、アメリカ企業に対する規制を強化するなど、対抗措置を取っています。
その結果、米中双方が経済的に大きな打撃を受けるだけでなく、世界中の企業やサプライチェーンにも混乱が波及し、貿易全体が滞る可能性が高まっています。
さらに、AIや半導体などの先端技術をめぐる競争も、ますます激しさを増しています。
アメリカは中国企業を金融制裁リストに載せたり、先端技術の輸出を禁止したりすることで、中国の発展を抑えようとしています。
一方の中国も、独自技術の開発を急ぎ、アメリカに依存しない産業基盤の構築を進めています。
こうした中で、もし台湾問題が浮上すれば、米中の対立はさらに深刻化するおそれがあります。
台湾が独立に近い動きを強めたり、アメリカが軍事支援を拡大したりすれば、中国は軍事的にも強く反発する可能性があります。
それによって、世界的なリスクが一気に急上昇するのです。
なぜ2025年が特に危険視されているのかというと、トランプ政権2期目の始動と重なり、アメリカも中国もそれぞれ国内問題の解決を優先しがちになるからです。
アメリカは、「トランプノミクス」による保護主義政策を通じて国民の支持を固めようとし、
中国も経済の減速や国民の不満を抑え込むために、「対アメリカ強硬策」を取る可能性があります。
もしこの米中対立が本格化すれば、世界中で部品や製品の供給網が寸断されるだけでなく、貿易や投資のルートまでもが分断されていきます。
そして同時に、「どちらの陣営につくのか」という選択を迫られる国も出てくるでしょう。
アメリカが保護主義政策を強める中で、台湾・韓国・ヨーロッパ諸国にとっても、アメリカと中国の間で自国の立ち位置が問われるという難しい状況が生まれます。
そしてもちろん、日本も例外ではありません。
このエスカレートする対立の中で、どのように立ち回るのか。
より高度で繊細な外交判断が求められる時代に突入しているのです。
2位 トランプの支配
2位は、「トランプの支配」です。
トランプ政権2期目では、トランプ氏に忠実な側近が揃った、結束力の強いチームが形成されています。彼らは思想や方針においても一致しており、トランプ氏の強硬な政策が進みやすい環境が整っています。
また、共和党が上下両院で多数派を占めているため、バイデン政権時代の施策を覆すなど、強引な政策運営が可能になっています。
トランプ政権が次に狙うのは「ディープステート(Deep State)」とされています。
これは、選挙で選ばれた政治家とは別に、高級官僚・メディア・独立機関などが強い影響力を持っているという疑念を意味する言葉です。
トランプ氏は、1期目の混乱は彼らによって引き起こされたと主張しており、その影響力を排除しようとしています。
言い換えれば、司法省やFBIなどの重要なポジションにも、自身に忠実な人物を配置し、政権への批判を封じようとしているのです。
このように反対意見を排除する姿勢は、アメリカの民主主義の根幹である「法の支配」や「政治的中立性」を揺るがすものとして、国内外から警鐘が鳴らされています。
政策がトランプ氏の意向によって左右されるようになると、協力的な企業には便宜を図る一方、批判的なメディアや企業には圧力をかける、という懸念も生まれます。
ただし、「トランプ氏が民主主義を崩壊させるような独裁者になるわけではない」とする見方もあります。
なぜならアメリカには、連邦議会や司法、軍幹部、独立したメディアなど、権力を監視・制限する制度が数多く存在しているからです。
また、アメリカは州ごとに強い権限を持っており、連邦政府だけで全てを決定できるわけでもありません。
とはいえ、もし2期目においてトランプ氏が自身の思い通りに政治を動かすようになれば、アメリカが長年守ってきた民主的制度の公正な運用や、独立機関の役割が徐々に損なわれていくリスクは否定できません。
一度「ルールを守らなくてもいい」という空気が生まれると、法の形骸化が進み、制度の修復が難しくなることも想定されます。
また、アメリカが掲げてきた「民主主義」や「人権」を重視するリーダーシップが弱まれば、国際的な協調体制にも綻びが生じるかもしれません。
アメリカ合衆国憲法の起草者たちは、「善良な人格と徳を備えた指導者」、そして「常に権力を監視する市民」の存在が、民主主義を守るために不可欠だと考えてきました。
これからのアメリカが「法によって統治される国家」であり続けるのか、
それとも「個人と恣意によって統治される国家」に傾くのか──
この問いは、決して他人事ではなく、国際社会全体に影響を及ぼす問題なのです。
1位 深まるGゼロ(G0)世界の混迷
1位は、「深まるGゼロ(G0)世界の混迷」です。
ここまで解説してきた各リスクは、すべてこの1位に内包される構造的な問題に集約されていると言えます。
つまり、世界が一つにまとまれず、各国が自国の生き残りを最優先に模索することで、かえって世界全体の結束が弱まり、不安定さが増していく──そうした根深い問題です。
この「Gゼロ」の状態が深まっている背景には、主に3つの大きな流れがあるとされています。
第1に、ロシアを国際秩序に統合できなかったこと。
冷戦終結後、アメリカやヨーロッパ諸国はロシアとの協力を模索しましたが、最終的にはロシアの反発を招きました。
ウクライナ侵攻をきっかけに、ロシアは経済的・軍事的に疲弊しつつも、その強硬姿勢を崩すことなく、「ならず者国家」のような存在となりつつあります。
第2に、中国が欧米型の政治制度や価値観に歩み寄らなかったこと。
中国は目覚ましい経済発展を遂げましたが、民主主義や人権の尊重といった欧米の原則には従いませんでした。
その結果、国内の統制を優先するあまり、人権・環境・国際協調といったグローバルな課題への対応が後回しになってきました。
第3に、格差の拡大。
これは先進国でも深刻な問題です。
グローバル化の恩恵を感じられない人々が増え、政治エリートや民主主義そのものへの不信感が広がっています。
経済格差や急激な技術変化に対する不安から、「まず自国を優先すべきだ」という声が高まり、トランプ大統領のように保護主義を掲げる指導者が世界各地で人気を得るようになっています。
こうした要因が複雑に絡み合い、大国が主導する枠組みや国際機関は十分に機能しなくなっています。
国連安全保障理事会、IMF(国際通貨基金)、世界銀行といった国際組織も、現在のパワーバランスを反映しきれず、存在感を失いつつあります。
その一方で、中国・ロシア・イランといった国々は、自国の利益を優先し、アメリカもかつてのように国際秩序の調整役を積極的に担おうとはしていません。
ヨーロッパや日本といった他の先進国も、国内の政治的混乱や経済的課題を抱えており、新たなリーダーになるには難しい状況です。
この「リーダー不在」の状態が続くことで、世界の不安定化が一層進んでいく可能性が高まります。
「Gゼロ」の世界が1位に挙げられたのは、2025年がその不安定のピークに差しかかる年であるという強い警告でもあります。
まとめ
日本もまた、大国同士のパワーゲームに振り回されるだけでなく、
平和と経済の安定を守るための「自立した道」を模索していくべきタイミングに差しかかっているのかもしれません。
これからの世界では、私たち一人ひとりが世界情勢と将来のリスクを的確に把握し、政治にも積極的に関わっていくことが、ますます大切になっていくでしょう。
そのために欠かせないのが、常に「学び続ける姿勢」──それこそが、これからの時代を生き抜く私たちに求められる「知的な備え」なのだと、私は思います。


コメント