
【究極の勉強法】マサチューセッツ工科大学の学生が実践する“科学的根拠のある”7つの勉強法とは?
私たちが唯一逆転する方法、それはただ一つ、知識をインプットすることです。知識をインプットし、それを活用すれば、私たちは何にだってなれる可能性があります。
これまで勉強してきた人というのは、年収、人間性、話し方、すべてにその影響が表れます。例えば、人と話していても「この人は頭がいいんだろうな」となんとなく分かりますよね。そして、その賢さは人生全体に影響を及ぼします。
多くの知識をインプットしている人の方が、全く勉強してこなかった人よりも、年収が高く、幸福度が高く、人生の自由度が高いというのは、すでにデータで証明されています。私たちはもう分かっているはずです。この世界では、「勉強した者勝ち」だということを。
しかし当然、ここで問題が出てきます。
「インプットした方がいいのは分かっている。でも、どうしても続けることができない」「うまくいかない」「思うように成績が伸びない」と感じる方も多いと思います。わかります。社会人なら資格勉強をしている方もいるでしょう。語学を習得したいと思っている方もいるでしょう。もちろん、学生で成績が伸び悩んでいる方や、受験生という人もいるでしょう。
ただ、私たちは現実を直視しなければなりません。
韓国でベストセラーになった『勉強が面白くなる瞬間』の著者であり、日本より受験競争が激しい韓国で、ソウル大学をはじめとする複数の難関大学の法学部や医学部に同時合格した実績を持つパク・ソンヒさんは、こんなことを言っていました。
「講義や講演会の際に、最も多く聞かれる質問があります。それは、『もう手遅れですか? 今からだと遅いですか?』というものです。
普通なら、『まだ間に合いますよ』と言うでしょう。しかし、あえて言います。『もう手遅れです』と。
当たり前でしょう。これまで勉強してこなかった人と、今までずっと勉強してきた人の間に差があるのは当然です。ちょっとやそっとで追いつけると思わないでください。」
本の中では、このように書かれていました。厳しい言葉ですが、確かにその通りです。
冗談のような話ですが、私の幼稚園・保育園時代からの親友に、東大に合格した人がいます。小学校までは同じで、家も近かったので、毎日一緒に登校するほど仲が良かったのですが、放課後に一緒に遊んだ記憶がほとんどありません。なぜなら、彼は小さい頃から塾に通い、勉強をし続けていたからです。まさに血のにじむような思いをして努力を続けてきたのです。
私たちは、こういう「すでに何年間もの積み上げをしている人たち」に挑まなければなりません。
マラソンで、すでに10km先を走られているところに追いつこうとするのですから、そう簡単ではありません。
では、私たちは何をすべきか?
やるべきことは簡単です。「限界まで勉強時間を圧縮し、効率性を極限まで追求する」必要があります。
大量の時間を確保するという王道の方法は、私たちには残されていません。そんな時間は、もう私たちにはないのです。
物量で対抗できないなら、圧倒的な“質”で勝負するしかありません。
「そんなことできるの?」と思ったかもしれません。私もそう思いました。しかし、勉強時間を減らしつつ、質を高める方法は確かに存在します。
今回は、マサチューセッツ工科大学(MIT)でコンピューターサイエンス、経済学、データサイエンス、ビジネスアナリティクスの学士号を取得しながらも、YouTubeの登録者数600万人を超える絶大な人気を誇るゴハール・カーンが、「勉強時間を減らして成績を上げる方法」を紹介していたので、それを皆さんに共有します。
7つの勉強法があります。この方法を使えば、私たちは無駄な時間を過ごすことなく、知識をインプットすることができます。
2025年時点で世界大学ランキング第2位のあのマサチューセッツ工科大学の学生が実践する勉強法。これは絶対に気になりますよね? でも、それは私たちにも実践できることなのでしょうか?
「とりあえずテキストの1ページ目から50ページ目を1行1句暗記してください。話はそれからです」と言われるんじゃないかと不安になるかもしれませんが、ご安心ください。今回紹介する7つのテクニックは、すべて私たちにもすぐに実践できるものです。しかも、その効果は絶大です。
私たちには、無駄な時間を過ごしている余裕はありません。
今回のゴハールの動画の中では、効率的な勉強法の他にも、「みんながやっているが、実は効果が薄い勉強法」も紹介されています。そして、動画の最後には、ゴハールの動画では触れられていなかったものの、今回のリサーチの中で「過去120年にも及ぶ研究の中で、最も効率がいい最強レベルの勉強法」が判明したので、それを1つ紹介します。
これから頑張ろうと思っている方も、すでに頑張っている方も、今やっている勉強法が本当に正しいのかを見直すという観点で、ぜひ今回のテクニックを学び、効率を極限まで高めてください。
では、ゴハール・カーンの7つの勉強法、1つ目から見ていきましょう。
1つ目のテクニック:勉強時間に囚われるな
「勉強時間は多ければ多いほどいい」と思うかもしれませんが、それは間違いです。
ゴハールはこう言っています。
ほとんどの人は勉強の“効果”には目を向けず、勉強時間の長さで自分の努力を測ろうとする。
確かに、勉強の効果を測るのは難しいですが、勉強に費やした時間を測るのは簡単です。だからこそ、多くの人が「長く勉強すれば成果が出る」と勘違いしてしまうのです。
例えば、5時間勉強したとしても、その時間ずっと蛍光ペンでマーカーを引いたり、教科書を書き写したりするだけの勉強では、成績はほとんど伸びません。
一方で、自分でクイズ形式で試したり、他人に教えるように記憶したり、アウトプットしようとした人では、習得度が全く違ってきます。
ゴハールの勉強法を見ていくと分かりますが、彼は何よりも「質」を最優先しています。なぜなら、彼自身が時間がない中でも、成績を維持しなければならないという状況にいたからです。
実際、ゴハールは高校を主席で卒業しています。しかし、高校時代には 11の大学専攻履修 をこなしていたそうです。
これは何かというと、高校生が大学レベルの授業を受け、テストに合格すれば大学の単位として認定される制度のことです。つまり、彼は高校の授業を受けるのと並行して、11個の大学の授業も受けていたということになります。しかも、そのうち5つは3年生の時に並行して受講していました。
大学に入ってからも、ゴハールは ダブルメジャー(複数の専攻を同時に履修)を選択し、膨大な量の授業をこなす必要がありました。それにもかかわらず、彼は すべての授業で成績を維持 していました。
これは普通の大学の話ではありません。あの 世界大学ランキング2位のマサチューセッツ工科大学(MIT)の話 です。
想像を絶するほどの努力が必要だったでしょう。
この状況を考えれば、彼が「勉強時間の長さ」ではなく、「質」にこだわっていた理由がわかるはずです。
「今日は6時間勉強できた!」と、時間の長さに満足してしまっていませんか? もしそうなら、まずはその考え方を変えましょう。
2つ目のテクニックからは、より具体的な勉強法に入っていきます。
2つ目のテクニック:テキストは後ろから読む
「え? 後ろから読む?」と驚くかもしれませんが、多くの人が勘違いしていることがあります。
それは 「教科書や参考書は最初から読まなければならない」という固定観念 です。
しかし、これは間違いです。
勉強に使う教科書や本は 小説ではありません。最初から順番に読む必要はないのです。
例えば、テスト勉強で「ヤバい! 時間がない!」と焦って、教科書を開くとします。
最初の方から中盤まではなんとなく覚えられたけど、後半は時間がなくてほとんど手をつけられなかった…。
こんな経験、ありませんか? 私もあります。
最初から読まなければならないという思い込みがあるせいで、時間が足りず、結局 重要なところを復習できずにテストに臨んでしまう のです。
この固定観念を捨てることから始めましょう。
では、どうすればいいのか?
答えはシンプルです。「テキストを後ろから読む」のです。
ゴハールは 「3回読み」 という方法を取っていると言っています。
① 最初に章の最後の要約を読む
ほとんどのテキストには、章の最後に 要約 や 重要ポイント がまとめられています。
まずは、そこを読んで「この章が何についての話なのか?」を把握します。
② 次に、見出しや太字、図を確認する
本文に入る前に、章の 見出し、太字、色で囲われている部分、図 をざっと見て、全体像をつかみます。
これは 「ファーストパス」 と呼ばれる方法で、いきなり本文を読むのではなく、要点だけを押さえます。
③ 最後に、本文をざっと目を通し、最初と最後の段落を読む
2回目の確認を終えたら、次は 「セカンドパス」 です。
この段階では、最初の段落を読み、本文はざっと目を通し、最後の段落を読みます。
この 3ステップ を踏むだけで、内容をかなり理解できるようになります。特に試験前には、この方法が非常に効果的です。
3つ目のテクニック:タスクをまとめる
こんなことをしていませんか?
- 英単語を覚える
- 英語の問題を解く
- リスニングをする
- 数学の公式を覚える
- 国語の読解問題を解く
このように、異なる教科を切り替えながら勉強していませんか?
実はこれは 非常に非効率 なのです。
ゴハールが言っていたのは 「思考のプロセスが違うものは、できるだけ切り替えるな」 ということです。
例えば、
- 文章を読む時と書く時
- 文章を書く時と数学の問題を解く時
これは脳の使い方がまったく違います。
脳にとって、この 思考の切り替え は 非常に負担 になります。
たとえば、作業中に話しかけられると、また作業に戻るのが難しくなること、ありますよね?
これは 「タスク・スイッチング・コスト」 と呼ばれる現象で、作業から別の作業に移ると、再び集中するのに 約10分から20分 かかると言われています。
これは 同じ教科内でも起こる ので、注意が必要です。
では、どうすればいいのか?
「教科」ではなく、「似たタスク」でまとめる のです。
例えば、
❌ 数学をやって、次に英語のリスニングをやる
✅ 数学と科学の問題をまとめて解く → その後に、歴史と英語のエッセイを書く
このように 脳の切り替えを最小限にすることで、集中力を維持 できます。
4つ目のテクニック:制限時間を設ける
勉強時間を減らす最も簡単な方法 は何だと思いますか?
それは 勉強時間を減らすこと です。
「おい、ふざけるな」と思うかもしれませんが、これは大真面目な話です。
ゴハールは 「パーキンソンの法則」 を活用すると言っています。
パーキンソンの法則とは、「仕事は締め切りギリギリまで拡大する」 という人間の習性を表したものです。
例えば、次のような経験はありませんか?
- 「レポートの提出期限は1週間以内」と言われたら、結局1週間かかる
- 「レポートの提出は1ヶ月以内」と言われたら、結局1ヶ月ギリギリまでやらない
このように、同じ量の作業でも、与えられた時間に合わせて人は行動してしまいます。
逆に、「今日・明日中に終わらせて」と言われると、「そんなの無理だ」と思いながらも、意外と間に合わせられることがありますよね?
これも パーキンソンの法則 です。
ゴハールが実践しているのは 「勉強の締め切りを自分で設定する」 ことです。
やり方:タイマーをセットする
- まず、その課題や作業にかかる時間 を予想します。
- そして 10%〜20%短い時間 を設定して、タイマーをセットします。
例:s
- 「この作業は3時間かかる」と思ったら、2時間30分に設定する
- 「本来60分のテストなら、50分で解いてみる」
こうすることで、「締め切り効果」を活用し、軽いストレスを自分にかけることができます。
これにより、集中力を最大限まで引き出す ことができるのです。
5つ目のテクニック:解けない問題は捨てろ
「解けない問題に時間をかけすぎる」
これは、テストや勉強でありがちな失敗です。
最善の方法は、その問題を捨てて次に進むことです。
特にまずいのは、1つの問題を解くために膨大な時間をかけ、もう後には引けなくなる状況。
これは心理学で 「サンクコスト効果」 と呼ばれる現象です。
サンクコスト効果とは?
- すでに投資した時間や労力を惜しんで、引くに引けなくなる心理現象。
- ギャンブルで「もう負けているのに、一発当てよう」とする心理もこれ。
- 会社が「赤字プロジェクトを続ける」のも、サンクコスト効果の典型例。
テスト中の失敗例
- 1つの問題に20〜30分かけてしまい、他の問題に手が回らなくなる。
- 結果、解ける問題すら時間切れで解けなくなり、全体の点数が下がる。
これは マサチューセッツ工科大学の学生でもやってしまう間違い だそうです。
つまり、私たちが無意識にやっている可能性は かなり高い ということです。
対策:迷ったら即「次の問題」に進む
- 解けないと感じたら、その瞬間に次へ進む
- 問題は順番通りに解く必要はない(最後の問題から解いてもOK)
- 大事なのは「時間と労力をかけていい問題か?」を見極めること
これは 仕事にも応用できる 考え方です。
時間をかけていいものかどうかを常に見極め、無駄なものは切り捨てる習慣を身につけましょう。
6つ目のテクニック:単純作業を先にやる
ゴハールによると、タスクには 2種類 あります。
① 単純作業(ルーチンワーク・暗記・整理など)
② 思考作業(レポート作成・アイデア出し・問題解決など)
ポイント:単純作業を先にやれ!
その理由は 「パーキンソンの法則」が関係しているから です。
単純作業は 時間が膨らむことが少ない ですが、思考作業は 制限ギリギリまで時間が膨らみやすい のです。
例えば、
- 「今日は3時間勉強する」と決めた場合
- 先に単純作業を1時間やる → 残り2時間で思考作業をやる
- こうすることで、時間を無駄にせず両方こなせる!
逆に、最初に思考作業をすると、その作業だけで3時間使ってしまう 可能性があります。
「単純作業を先にやるか、思考作業を先にやるか」には意見が分かれますが、ゴハールは長年 単純作業先派 で、これで成功しているそうです。
ただし、人によっては「単純作業を少しだけ(5〜10分)やってエンジンをかける」のもアリかもしれません。
7つ目のテクニック:復習は「分からないところだけ」をやる
やってしまいがちな間違い
- 復習のときに「すべてのノートを読み返す」
- すでに分かっている部分まで復習してしまう
これは 時間の無駄 です。
正しい復習法
- 普段の学習中に「分からない部分」に印をつける
- 復習時には、その部分だけを重点的に復習する
なぜこれが重要なのか?
すでに理解している部分は 何度繰り返しても記憶に残りにくい からです。
逆に、分からなかったところを集中的に復習することで、記憶の定着が飛躍的に向上します。
授業中のノートの取り方も重要
- 先生が黒板に書いたことを 全部写すのはNG
- 大事なのは 「何が分からないのか?」を把握すること
本当に優秀な生徒は、授業中に黒板の文字を必死に書き写さず、理解することに集中 しているのです。
 | プロテイン WPC エクスプロージョン 3kg ミルクチョコレート味 ホエイプロテイン 3キロ 最安値 大容量 筋肉 タンパク質 高たんぱく 運動 ダイエット 置き換え 男性 女性 子供 こども 価格:7470円 |
まとめ
ここまで、ゴハールの「7つの勉強法」を紹介しました。
この方法を実践すれば、勉強時間を減らしながらも、圧倒的に効率よく知識を吸収できます。
さて、ここからは 過去120年の研究から判明した「最強の勉強法」 を紹介します。
その方法とは… 「アクティブリコール」 です!
最強の勉強法:アクティブリコール
ここからは、過去120年にも及ぶ研究の中で判明した「最強の勉強法」について紹介します。
その方法とは、「アクティブリコール」 です。
アクティブリコールとは?
アクティブリコール(Active Recall)とは、「能動的に思い出す」 ことを中心とした学習法です。
要するに、「あれ、なんだったっけ?」と自分の記憶から引き出す回数が多ければ多いほど、記憶に定着しやすい という理論に基づいています。
私たちは、普段の勉強で「理解しよう」とはしますが、「思い出す」ことにはあまり意識を向けていません。
しかし、記憶を定着させるためには、「インプット」ではなく、「アウトプット」することが鍵 になるのです。
アクティブリコールの科学的な証拠
この学習法が効果的であることは、1939年からすでに研究されていました。
そして、2010年のある実験では、以下のような結果が出ています。
- グループA → ノート作成やマーカーを引くなどの「普通の学習法」を実践。
- グループB → 学習後に小テストを実施し、アクティブリコールを中心に勉強。
- その1週間後に本番のテストを実施した結果、グループBの成績は30%向上 していた。
つまり、普通の勉強法をするよりも、「思い出す回数を増やすだけで、成績が30%も向上する」 ということです。
では、実際にアクティブリコールをどのように取り入れればよいのでしょうか?
アクティブリコールの具体的な実践方法
1. フラッシュカードを作る
最も簡単な方法の一つが、「フラッシュカード(単語カード)」を使うこと です。
- 表面に質問、裏面に答えを書く
- 問題を見て、答えを思い出そうとする
- 答えを確認し、間違えたら再度やり直す
これは昔からある方法ですが、その効果は科学的に証明されています。
特に 「自分で作ったフラッシュカード」 は、記憶の定着率が高いです。
例えば、英単語を覚えるときには、市販の単語帳を使うのではなく、自分で問題を作って、アクティブリコールを実践する のが効果的です。
2. 本を閉じてノートを取る
次におすすめの方法が、「本を閉じてノートを書く」 ことです。
これは、ただノートを写すのではなく、一度内容を理解した後、本を閉じて、自分の言葉でノートを書く というやり方です。
具体的なステップ
- 教科書や参考書を読む
- 本を閉じて、頭の中で思い出しながらノートに書く
- 書いた後、本と照らし合わせて間違いを確認する
ポイントは、「人に説明するつもりでノートを書く」 ことです。
実際、人に教えるつもりで勉強すると、記憶の定着率が格段に上がることが分かっています。
3. 自分の言葉で説明する
これは、フラッシュカードやノート作成よりもさらに強力な方法です。
「自分の言葉で誰かに説明する」 ことで、アクティブリコールを最大限に活用できます。
例えば…
- 勉強した内容を友達や家族に話してみる
- 誰もいなければ、鏡の前で自分に向かって説明する
- 音声を録音して、自分の説明を聞いてみる
この方法を使えば、「理解したつもりだったのに、実は説明できない」と気づくことができます。
これは、自分の記憶の穴を埋めるのに非常に役立ちます。
4. 通勤・通学中に思い出す
忙しい人でも簡単にできるアクティブリコールの方法があります。
それは、「通勤・通学中に勉強した内容を頭の中で思い出す」 というものです。
例えば…
- 昨日学んだことを、頭の中で復習する
- 「あれってどういう内容だったっけ?」と自問自答する
- 自分なりの例を考えてみる
これだけでも、アクティブリコールの効果を得ることができます。
私自身も、通勤中に「昨日読んだ本の内容を思い出す」ことを習慣にしたところ、記憶の定着が格段に良くなりました。
 | 価格:8480円 |
アクティブリコールの効果を最大化するために
フラッシュカード、本を閉じてノートを取る、自分の言葉で説明する…。
これらの方法を 組み合わせる ことで、さらに効果を高めることができます。
例えば、
- 本を閉じてノートを作成(アクティブリコール)
- そのノートをフラッシュカードにする
- 友達や家族に説明する
- 通勤・通学中に頭の中で復習する
これらを実践することで、記憶の定着率が劇的に向上します。
また、「思い出す頻度を増やす」 ことも重要です。
1回思い出しただけでは、記憶には定着しません。
定期的に「アクティブリコール」を繰り返すことで、長期記憶としてしっかり脳に刻まれるのです。
まとめ
ここまで、ゴハール・カーンの「7つの勉強法」と、科学的に証明された「最強の勉強法・アクティブリコール」について紹介しました。
ゴハール・カーンの7つの勉強法
- 勉強時間に囚われるな → 勉強時間の長さではなく「質」を最優先
- テキストは後ろから読む → 効率的な3回読みを実践する
- タスクをまとめる → 「科目単位」ではなく「思考プロセス単位」で勉強する
- 制限時間を設ける → パーキンソンの法則を活用し、締め切りを設定する
- 解けない問題は捨てる → サンクコスト効果に惑わされず、効率的に勉強する
- 単純作業を先にやる → 逆パーキンソンの法則を利用し、効率よく進める
- 復習は「分からないところだけ」をやる → 時間を無駄にせず、記憶を定着させる
そして、最強の勉強法 「アクティブリコール」 を活用することで、さらに効率的に記憶を定着させることができます。
最後に…
今から勉強を始めようとしているあなた。
「もう手遅れかもしれない…」と不安になっているかもしれません。
しかし、完全に手遅れではありません。
私たちには 「質を最大化する勉強法」 があります。
勉強を「ただの作業」にせず、効果的な方法で進めていきましょう。
一瞬、心を燃やして、人生の成功を掴み取るのは、あなた次第です。
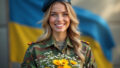

コメント